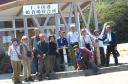急な登山口 |
 権現平で歓談 |
 権現平で歓談 |
 権現平で歓談 |
 権現平で歓談 |
 おでんをいただく |
 全員集合 |
 権現平から 丹沢を望む |
 南山から 横浜方面を望む |
 長い下り坂 |
山行記録に戻る
2.榛名/蛇ケ岳(1229m)・鬢櫛山(びんぐしやま)(1350m)~掃部ケ岳(かもんがだけ)(1449m) (干支山行)
期 日:1月12日(日) 日帰り 曇り後晴れ
参加者:L安瀬はる江、SL神谷敏裕、助廣弘子、山口音子、横川芳江、繁村純夫、繁村美知子、中村博雄、金子盛次 計9名
コース:橋本駅7:15=車=蛇ケ岳登山口9:50~10:03―蛇ケ岳山頂10:17~20―蛇ケ岳登山口10:30=車=鬢櫛山登山口10:35~45―鬢櫛山山頂11:40~45―硯岩12:30~35―掃部ケ岳13:22~50―記念公園駐車場14:35~50=車=橋本駅17:20 貸切タクシー代 7400円/一人
干支山行10回目。以前、蛇ケ岳に登っていたのですぐに決定。巳年生まれの方が2名ご参加。榛名山は榛名山系の総称で外輪山と溶岩ドーム群で形成されている。その最高峰の掃部ケ岳に鬢櫛山から繋げるコースに予定を変更。期待した雪は一部だけだった。榛名湖湖面は半凍結して、鉛色だった。
SLを先頭に蛇ケ岳は一登りで目的を達成。今年は人気で、通過点のような山頂では一グループと出会った。山名の由来は不明。すぐに下山。鬢櫛山登山口まで車で移動。鬢櫛山山頂からの南西のバリエーションルートは急な岩稜帯もあった。下部はなだらかな笹原。ルートは明瞭だった。林道に降り立ち硯岩下までは地形図の破線図を辿る。道標もあり、歩き易い。榛名山のシンボル・硯岩からは全容が見渡せ、遠望もあった。ここからの蛇ケ岳の山容はとぐろを巻いた蛇のように見えた。
掃部ケ岳への登りは階段が多く、空腹もあり、難儀した。上部はうっすらと雪があり、登山道は凍結していた。山頂に着くと陽射しも強くなり、無風だった。南側の大パノラマを前に昼食。北側は樹間越しに日光、武尊、谷川の白嶺がピカピカ。下山時、岩場で滑り、ひやりとしたが、立木に助けられた。
榛名湖周辺にポコポコ並ぶ山の眺めは類稀。特異な山容が方向により変わり、楽しい山です。熟練者揃いで登りは体力が少々不安?下りは技術力が高くトータルコースタイムは標準の8割でした。(安瀬はる江)
山行記録に戻る
3.横浜/円海山~天園
期 日 :1月16日(木)日帰り 曇り
参加者:L榎本美智子、SL森田隆仁、助廣弘子、油田まりこ、宮崎博之 計5名
コース:港南台駅9:35―いっしんどう10:25―大丸山11:25昼食11:50―自然公園12:20-市境広場12:30―天園13:00―瑞泉寺13:55見学―鎌倉宮14:35バス14:50発―鎌倉駅15:00解散
小田急線のトラブルがあったが9時30分過ぎには集合出来た。曇り空で寒いと言う予報だが思ったほど寒さを感じず登山口を目指す。駅前のバスターミナルを左に直進、環状3号線を渡ると消防署が見えてくる。消防署の脇を登ると案内板が見えそこからは富士山が見えるのだが全くどこに富士山やら残念、横浜市最大の森と言われる瀬上、氷取沢、金沢市民の森が鎌倉まで続き様々なトレイルが整備されている。我々はその中のビートルズトレイルと六国峠ハイキングコースをつないだ円海山から天園の尾根を歩いた。アップダウンの少ない歩きやすく所々箱根、丹沢連山が見渡せる。大丸山は横浜市最高峰156.8m階段上りがあり頂上は金沢区方面の港が広がっていて気持ちの良い展望台でベンチもあり昼食タイム。曇っていた空が一瞬青空を見せてくれて嬉しい気分にさせてくれた。メンバーに鎌倉に熟知しているM氏の案内で自然観察センターへ自然に関する展示やイベント企画する施設だそうで施設内は綺麗でトイレを借りた。トイレが少ないコースなので有りがたい。そこから市境横浜市と鎌倉市の境に杭があった。天園に向かう途中広大な横浜霊園を見下ろしながら余りの広さに驚くばかりだった。天園は過去にあった茶店もなくなり寂しい限りだ。瑞泉寺へ下り200円の拝観料で見学する。水仙は咲き始め色合いの違う椿や蝋梅やミツマタの花が見られた。鎌倉宮ではバスがタイミング良く出るので乗車して鎌倉駅に向かった。割と駅まではスムーズだった。今回春にはほど遠い冬枯れの鎌倉ハイキングだったが目を見張る様々な巨木やアオキの赤い実、ヤブツバキの楚々とした花が楽しめた。鎌倉を歩き尽くしたM氏のサポートでより深く鎌倉を楽しめたハイキングでした。(榎本美智子)
山行記録に戻る
4.三浦アルプス/仙元山~乳頭山
期 日:1月25日(土) 日帰り 曇り
参加者:L松本悦栄、SL小磯登志子、英賀昇子、岩月宣雄、近藤由美子、杉江秀明、中村博雄、宮崎博之、油田まり子 計 9名
コース:JR逗子駅8:20=<バス>=風早橋バス停8:27~8:35―仙元山8:49~8:55―戸根山9:27―観音塚9:44~9:50―高塚9:59―休憩10:00~10:08―大桜(昼食)10:50~11:16―鉄塔NO.34―三国峠12:03―乳頭山12:07~12:14―田浦梅の里12:50―展望台12:53~12:58―JR田浦駅13:34~13:37乗車(解散)
三浦アルプスを知るきっかっけは、昨年10月支部仲間から誘われ森戸川のお花探しからでした。また、支部内でこのエリアの愛好者数人から情報や地図を頂くなど、興味が益々高まり単独で入山することが多くなった。三浦アルプスの愛好者が増えることを願い計画した。
逗子駅バス乗り場で12月から新会員となったMさんを紹介し乗車予定のバスを待った。風早橋バス停で降車して身支度を整え隧道に向かって歩き出す。約100m歩くと左側にある階段が登山道に通じる道になります。15分ほどの登りで仙元山に着いた。山頂から振り向くと相模湾。曇天の為、富士山を拝むことが出来なかったが、江の島が遠望でき海の眺めは素晴らしい。
ここから少し下り100mの急斜面の長い階段を登ると戸根山に着いた。立休みをしてから二つのコブを越えるとタブノキと馬頭観音と千手観音が待っている観音塚です。この先も六つのコブを越え10:50に大桜に着いた。予定では鉄塔34の辺りで昼食かなと思っていたが、しゃがむと周りの木々が風よけになってくれるので少し早いが昼食にした。昼食を済ませ乳頭山に向け歩き始めた途端、おお人数(30人位)が登ってくる。道を譲り団体さんを待っていると通過に数分を要した。
鉄塔34を過ぎ三国峠での指導標は0.1kで乳頭山の表示。そしてひと登りで山頂に着いた。山頂からは東京湾と横浜方面が見渡せる。ここで集合写真を撮り下山開始。直ぐに東逗子駅方面の案内板があるが、直線の道が広くこのまま進んでしまいそうになるため(中尾根(バリ)の道)要注意です。我々はこの分岐を右に、そして次の分岐も右に。この先は今回の核心部(ちょっとオーバー)である岩っぽい下りで、ロープを使い慎重に降りる。これが5カ所あるがその先には危ない箇所はなく田浦梅の里に到着する。梅の時期は2月なので咲いていないと思ったが、白梅2本が開花していた。それから展望台に上って360度の眺望を楽しんだ後は、芝生広場でトイレ休憩とした。ここでのんびりお茶をしたいところだが、冷たい風に負け早々JR田浦駅へと向かった。
*三浦アルプスの情報を詳しく紹介しているのが「みろく山の会」さんのホームページです。
コース紹介や開拓の歴史・地図等詳しく掲載しています。(松本悦栄)
山行記録に戻る
5.東北宮城/荒雄岳
期日:1月25日(土)~26日(日)一泊二日 晴
参加者:L萩原克己、SL神谷和男(支部外)、神谷敏裕、後藤勝弘、飯嶋光江、岩井初江、横川芳江、田中恵美子(支部外) 計8名
コ一ス:26日(土)宿8:30-林道入口8:45~9:00-八ッ森コース登山口11:00~11:20-林道入口12:45~12:55-宿13:10-バス停=鳴子温泉解散
費 用:宿代金¥106360、バス代金往路400×8=¥3200、復路¥5760+¥400×2=¥6560
宿は昔ながらの素朴で静かな雰囲気の漂う露天風呂のある昔文豪等が愛した小さな宿で当日は私達8人の貸し切りでした。
26日は前日下見をした林道の入口から除雪をしていないのでスノ-シュ-、ワカン(私がワカン装着にとまどって時間が掛かり)を付けて登つて行きましたが地熱発電所の前を通り送電線の当たりに来ると展望が開け、北東方向に以前に登ったアルペン的景観の禿岳、又その背後に過去3回登っている東北で三番目に長い白銀の神室連峰に圧倒されました。
今年は4月には3回春山を計画しているので神室連峰に行けませんが来年の四月に神室岳避難小屋(泊)1泊2日を考えています。
さらに緩い林道を登って行くと荒雄岳登山口を示す標識があり、帰りのバスの時間等を考えたら無理なのでそこで昼食を取り引き返しましたが、3名だけすこし先の広々とした台地迄行きましたが、夏時間でも頂上まで1時間30分弱かかります。
帰りのバス停近くの食堂であかマムシをペットボトルに入れて飼っているのには驚きましたね!
ある程度の標高のマイナ-の雪山には連泊くらいしないと頂上まで行くのは難しいですね!(萩原克己)
山行記録に戻る
6.日光/雲竜渓谷
期 日: 2月1日(土) 日帰り 快晴
参加者:L松宮俊彦、SL松本悦榮、岩月宣雄、岩井初江 計4名
コ-ス:東武日光駅8:30=<タクシー>=雲竜渓谷登山口8:45~55-稲荷川第10砂防堰提-日向砂防ダム分岐9:55~洞門岩10:10~20-河原コースー雲竜渓谷入口(降下点)10:55~11:25-雲竜氷瀑12:00~25-雲竜渓谷入口13:00~15-(林道コース)-洞門岩13:45~50-(林道コース)-日向砂防ダム分岐-(林道コース)-見晴台14:20-雲竜渓谷登山口14:55~15:10=(タクシー)=東武日光駅
費 用:各自電車賃、タクシー(2700+3260)/台
日光女峰山山麓を東南に稲荷川が流れている。その最上流、標高約1600mに雲竜滝があり冬季には氷結する。今回はその氷瀑を真下から眺めようという山行である。
東武日光駅に集合しタクシーで雲竜渓谷登山口へ。登山口ゲートへの細い道には1kmほど手前から路上駐車があり、駐車場も満杯。氷瀑時期は1月末から2月と限られ、週末も重なりさすがの人出だ。ガイドツアーもいくつか入っているようだ。
登山口(右岸)を出発しすぐに堰提を渡り左岸に移り上流に進む。途中広い河原で渡渉(幅1.5m程度)し再び右岸に戻る。河原からは雪のついた女峰山の岸壁が眺められた。河岸を登ると日向砂防ダム分岐で、そこから林道を少し歩くと洞門岩に到着。ここからは林道コースと河原を行くコースがある。予定は林道だったが、人手が多いし流量や天候も安定しているので、チェーンスパイクを着けて河原コースを行くことにした。河原はトレースも明瞭、前後に人もいて間違える心配は無かった、渡渉は2か所(幅約1.5m)あった。11時前に雲竜渓谷入口の広場に到着したが、20人ほどの人がいた。前方に目をやると、これから歩く雲竜の渓谷や河原を歩いているパーティーを見下ろせた。周りは若者が多く、足回りはチェーンスパイクが多かったが、我々はアイゼンに変えていよいよ雲竜渓谷に入っていった。
薄い雪に覆われた河原を進むと、高さ3~5mほどのツララや氷柱が河原の端のあちこちに出てきた。それらを眺めたり写真に撮ったりしながら歩いて行くと30分弱で雲竜瀑の下の広場に出た。前方に滝の上流部分だけが見えるが滝壺部分は見えず、そこに行くためには、横から急こう配の細い道を登らなければならない。ユックリ注意しながら登ったが、やはりアイゼンのおかげで足が安定している。10分程で雲竜滝の全貌が見え、すぐに滝壺部分(凍っているが)に到着。
下から眺めると、凍った部分がごつごつしており陽に照らされて青みを帯びて光っている。全貌が眺められる場所でまったりコーヒータイム。滝は上方が狭く下に行くに拡がっており、全体としての姿形が整っている。それが人気の理由なのだろう。
名残惜しいが戻ることに。細い急こう配の下りはアイゼンを引っ掛けないよう注意しながらゆっくり下る。下の広場に着いて一安心。ここからは渓谷のツララや氷柱、それにきれいな水の流れを楽しみながら渓谷入口まで戻った。まだこれから渓谷に向かうグループも多く人気のほどがうかがえる。戻りは右岸の林道を一気に下ることにした。林道は薄い雪の部分、凍っている部分、雪のない部分が交互に出て来て歩きにくい。ゲートの30分程手前に見晴台があり、振り返って歩いてきた道を確認したりしながらタクシーの予約をした。渓谷登山口のゲートに着きしばらくするとタクシーが来て、東武日光駅まで運んでくれ、ここで解散となった。(松宮俊彦)
山行記録に戻る
7.丹沢/戸沢林道 (読図講習会)
期 日:2月9日(日)日帰り 快晴
参加者:L神谷敏裕、神谷友子、要 加月、水内好江、宮﨑博之、英賀昇子、太田久枝、山崎 稔 計8名
コース:大倉バス停10:00~10:20-倉見山荘分岐11:35~11:45-新茅山荘12:30~12:55-作治小屋13:10~13:25-戸沢分岐13:35~13:55-大倉バス停15:20
費 用:小田急線町田駅起点(町田=渋沢)\960、(渋沢駅=大倉)\500
昨年に続き読図講習会を実施。大倉バス停付近で、まず地形図を使って整置の仕方や磁北線、高度などを確認。更に地形図とプレートコンパスを使って、大倉から望める雨乞岳や表尾根の三ノ塔などを確認した。
大倉バス停から風の吊橋を渡り戸沢林道に入る。参加者が順番にリーダーを担当し、予め地図上に記載した目標地点まで歩く。各地点では、全員で地図を見ながら周りの地形や目標物を確認した。
昼過ぎに新茅山荘に到着。誰もいないのかと思ったが小屋番のおじさんがいて、小屋奥のテラスで昼食を摂ることを快く応じてくださった。土日だけだが20年以上も小屋番をしているとのことだった。ムササビが住む巣箱などを見せていただいた。
午後も戸沢林道を歩き、戸沢の分岐まで行って元の道を大倉まで引き返した。朝方は冷え込み路面も凍結していたが、昼頃からは日差しで温かく学習会にはよい天候だった。参加者の皆さんがお互いに教えながら、真剣に取り組んでくださった講習会だった。(神谷敏裕)
山行記録に戻る
8.湘南/鷹取山~湘南平2
期 日:2月15日(土)日帰り 晴れ
参加者:L榎本美智子、SL武末範子、SL大貫文正、森田隆仁、矢澤孝二、助廣弘子、杉江秀明、若松節子、大槻章夫、伊藤有子、油田まりこ、英賀昇子、瀧沢正明、中村博雄、鬼束しづ子、中村公子、宮崎博之、延澤英明 計18名
コース:JR.二宮駅南口9:05発平塚行きのバスー生沢(いくさわ)下車9:20―鷹取山10:30―鷹取神社―ゆるぎの丘11:20-11:45―霧降の滝12:00―松岩寺12:20-万田の池13:15―湘南平13:55-14:20―大磯駅15:00 解散
二宮駅からのバスは我々18名の貸し切り状態で地元の利用者は少ない。生沢停で下車後進行方向とは反対の道に戻り里山風景の中を歩く。谷戸川渓谷に沿って野鳥が生息している森があり野鳥の会のグループとすれ違うだけの静かな道、野鳥のさえずりが心地良い。
鷹取山の頂上は特徴がなくそれでも三角点を確認した。鷹取山の表示は木の枝のテープに巻き付けられたお粗末なものだった。その先に鷹取神社があり銀杏の実が敷き詰められたように落ちていて酒のつまみ?に拾う人がいたけど食べられたかどうか?ゆるぎの丘までは急下降の落ち葉で滑りやすい道を慎重に歩く。ゆるぎの丘は開けた展望地で菜の花が少し咲いていただけで菜の花畑は期待できなかった。巨木のエノキが広場の象徴のように存在感を示していた。
霧降の滝は下から見上げると大きな岩から水がチョロチョロで滝と言うにはほど遠い。松岩寺から不動川を渡り万田の池を目指す。朽ち果てた植物が散在し綺麗な池とは言えなかった。湘南平の鉄塔が間近に見えてきたが取り付きは不安定な橋を渡り大木をまたぎジグザグの山道を登り詰めると湘南平の駐車場へ出た。ちょうどバスが出るところで4名がバスで下山、他のメンバーは雄大な湘南平の景色を堪能してから下りは古墳群のコースを下山し大磯駅に着いた。
今回は舗装道の長いコースできつかったが里山風景と春を感じながら楽しめたハイキングだった。残念なのは富士山に雲がへばりついて美しい富士山を見られなかった事が心残りだった。(榎本美智子)
山行記録に戻る
9.北ア/上高地スノーハイキング
期 日:2月21日(金)~22日(土) 一泊二日
参加者:L松宮俊彦、SL神谷敏裕、松本悦栄、小磯登志子、矢澤孝二、繁村純夫、繁村美知子、岩月宣雄、助廣弘子、岩井初江、横川芳江、計11名
コース:
21日:松本駅バスターミナル13:05=(バス)=沢渡バス停14:10-ペンションしるふれい(泊) 他に車組2台
22日:しるふれい7:50=釜トンネル入り口登山口8:00~8:10-上高地トンネル出口8:55~9:05-大正池ホテル9:40~45-バスターミナル(夏)10:30~40-河童橋10:45~11:20-焼岳分岐11:50-帝国ホテル12:10-大正池ホテル12:40~45-上高地トンネル13:00~10-釜トンネル13:40=ペンションしるふれい(解散)=沢渡バスターミナル15:05~15:17=松本バスターミナル16:25
費 用:ペンションしるふれい(9300円)+旅費 スノーシューはレンタル可
上高地の冬景色を見みたいという思いでこのハイキングを企画。幸い沢渡に以前支部で利用したペンションがあり、そこで登山口への送迎やスノーシューレンタルもできることが分かり、計画を具体化した。
21日:バス組と車組(2台)に分かれ、宿には午後3時過ぎには全員集合。今晩の泊りは我々だけで談話室で美味しい野沢菜等頂きながらくつろいだ。他のパーティーの情報で、林道は圧雪してありスノーシューは不要とのことなので、軽アイゼンのみで行くことにした。
22日:朝食後宿の車2台に分乗し、登山口での釜トンネルの入口へ。トンネル内はアイゼン不要、また点灯しており懐中電灯も不要。トンネルは想定以上の登りで今日の標高差約200mのうち半分以上がこのトンネル内だった。二つ目の上高地トンネル出口で軽アイゼンを装着した。左を梓川右を急傾斜の林の間、平らな道を歩いていくと大正池が見えてきた。更に、林間の道を行くと左に雪をかぶった帝国ホテル、その先で夏のバスセンターの広場に出た。その少し先が今日の目的地河童橋だった。
穂高方面は2合目から下しか見えなかったが雪原の中を流れる梓川が、夏とは違う趣があった。昼食を取り写真も撮りした後、帰路は右岸の川沿いの道を進んだ。この道は圧雪が少ない分歩く面白さはあった。ウエストン碑を目標にしたが知らぬ間に通り越してしたようなのでそのまま進むことにし、焼岳分岐、田代橋を渡り帝国ホテルの横で往きの道に合流した。それからは林道歩きを続け、大正池を過ぎ、上高地トンネルに着き。そこで軽アイゼンを脱いだ。釜トンネルは下りになるので全員快調に歩き、2時前にトンネルを出ると、途中から連絡した宿の車が待っていた。宿に戻り談話室でユックリ荷物の片づけをし、談話していると宿の方が野沢菜漬けやお茶を出してくれた。そこで解散とし、車組とバス組に分かれそれぞれ帰途についた。
天候に恵まれ、無事行程を終えることができたが途中雪崩の頻発地帯も通った、また冬用トイレは場所と数が限られているので、事前の把握が不可欠であろう。宿舎のしるふれいは価格もサービスも満足できた。(松宮俊彦)
山行記録に戻る
10.奥多摩/青梅丘陵~栗平 (花山行)
期 日:2月25日(火)日帰り 晴れ
参加者:L安瀬はる江、SL杉江秀明、SL繁村美知子、助廣弘子、山口音子、繁村純夫、中村博雄、伊藤和良、大貫文正、曽我幸子、鬼束兼一、鬼束しづ子、榎本美智子、黒澤壽子、水内好江、大槻章夫、竹田早苗、小林洋子、中村和江、中村公子 計20名
コース:青梅駅9:15-金毘羅神社9:40~45-展望広場9:50~10:00-矢倉台9:45~11:10-三方山山頂(454.3M)12:10~17-林道分岐12:22-栗平林道12:30~55-群生地13:00~45-ノスザワ峠14:20~25-石神前駅分岐14:50-石神前駅15:30~50
当日は寒波が去って、温暖な陽気と陽射しを好むという絶好の福寿草日和だった。このルートは4/5のトレラン大会に向けて、随所にコース案内があり、惑わされる所もあった。
矢倉台までは快適な遊歩道で大勢散歩されている。途中の展望地からは都心のビル街が霞んでいた。休憩をとった矢倉台では富士山の頭がくっきりと見えた。ここから先は暗い植林の中、小刻みな上下を繰り返していく。平日で行き交う登山者はまばらだった。辿り着いた三方山山頂は登山道からそれた立木に囲まれた小ピークだった。お昼時だったが手狭なので、先送りにする。ここから200m位先で登山道から分岐して、鉄塔巡視路で栗平林道へ下りた。しかし、下りに時間がかかった後部隊がここで分岐せず直進した。気が付いて走って追いかけ、10分後に出逢えた。30分程の顛末だったが、全員、林道に下り立てた。初心者が多かったので、大勢での歩き方を確認し合った。
気を取り直し、福寿草の咲く群生地に急ぐ。昼前後から開花するときく。タイミング良く、全開した沢山の数が咲いていた。青梅草の見分けは難しく、福寿草と交配されて数は少ないようだ。栗平集落の民家は三戸で長閑な開けた場所だった。集落中央の芝生広場で遅い昼食が摂れた。
帰りはバス時刻に合わせると慌ただしいので、集落上の稜線をノスザワ峠まで戻り、三方山の先で石神前駅に向かった。小砂利の道だったが皆さんの頑張りで足並みを揃えて歩き、石神前駅に到着した。(安瀬はる江)
山行記録に戻る
11.足利/行道山
期 日:3月1日(土)日帰り 晴れ
参加者:L萩原克己、SL後藤勝弘、松宮俊彦、助廣弘子、油田まり子、計5名
コース:JR足利駅9:50=(タクシー)=行道山浄因寺登山口10:10-浄因寺11:00-行道山山頂11:30~12:00-大岩山12:30-大岩山毘沙門天13:00-両崖山14:30-足利織姫神社15:20-足利駅15:50解散
それぞれ休日おでかけフリーキップかジパングを購入して足利駅へ集合、3時間かかり、足利は遠かった。帰りのバス便がないので当初下山する予定だった行道山浄因寺までタクシーで入り、そこから歩いて当初登る予定だった足利織姫神社に下山するコースに変更。タクシーを降りると10数名のツアーの団体が準備体操をしており、この人たちとは後になり先になりして、ずっと一緒だった。浄因寺は「関東の高野山」とも呼ばれる行基上人開祖の名刹、岩の上に乗っかる小屋・清心亭と小さな橋が面白い。葛飾北斎がここを題材にいくつもの浮世絵を作っているとは、初めて知った。コースはおおむね断崖の上を行く道で、しばしば現れる長い階段の上り下りにうんざりしながらも、ポカポカ陽気に眺めは抜群とあって、気分よく歩く。行道山の山頂のベンチで昼食。眼下に広がる関東平野と雪をかぶった榛名山や上越の山々が素晴らしい。日光白根山がきれいに見えていた。大岩山毘沙門天の仁王像が修復中で、大切に守り続けたいという若いお坊さんの熱意に打たれて、我々も多少の寄付をする気にさせられた。両崖山は足利城址とのこと、沢山の人が参拝に訪れていた。足利織姫神社は赤の色が際立つ華やかな神社だが、我々は縁結びには関心なく、さっさと通過、ここから駅までの街歩きが疲れた足に痛かった。(助廣弘子)
山行記録に戻る
12.奥多摩/大岳山 (本部合同)
期 日:3月8日(土) 日帰り 曇り
参加者:L神谷敏裕、SL大貫文正、SL松本悦栄、伊藤知良、山口音子、横川芳江、杉江秀明、伊藤有子、支部外8名 計16名
コース:武蔵五日市駅8:22=大岳鍾乳洞入口8:49~9:00-大名子ノ頭9:50~9:55-高岩山10:47~10:53-上高岩山11:25~11:40-芥場峠11:58-大岳神社12:43~12:57-大岳山13:15~13:25-大岳神社13:43~13:50-白倉分岐14:13-大嶽神社15:30-白倉15:40-払沢の滝入口16:13~17:04=武蔵五日市駅17:28
当初は大岳鍾乳洞入口からサルギ尾根を登り、大岳山からは馬頭刈尾根に向かってつづら岩から千足に下りる予定だったが、夕方から降雪予報のため、白倉分岐から白倉に下りる短縮ルートに変更した。
サルギ尾根はいきなり急な階段を登っていくので、ゆっくりと登る。残雪は殆どない。大名ノ頭まで急登が続くが、ここを過ぎると今度はアップダウンを繰り返しながら登っていく。上高岩山の展望台で暫し休憩。この展望台は多人数が座れるので早めの昼食を摂る。上高岩山を過ぎると所々山道が残雪で覆われている。最初は雪道だったが、芥場峠を過ぎると凍結箇所が多く坂道は非常に歩き難い。慎重に歩いてなんとか大岳神社に到着。
大岳神社から先は更に雪が多そうなので、各自軽アイゼン、チェーンスパイクを装着。山頂までは岩部分を除いて雪道だった。僅かではあるが時々雪が舞い始める。山頂にいたのは一組だけ。全く展望がないので集合写真を撮って早々に下山開始。大岳神社からは馬頭刈尾根方面に向かう。白倉分岐に近づくと次第に雪は少なくなる。白倉分岐から麓に向けて下山。分岐から少し下ったところで軽アイゼン、チェーンスパイクを外し、更に下山を続ける。車道に出ると大嶽神社があり、更に10分下るとバス停に至る。
バス停に到着すると同時に大粒の雪が降り始める。事前に調べていたバスの時刻は平日ダイヤだったらしく、次のバスは1時間以上ないことが判明。調べると払沢の滝入口から30分後にバスがありそうなので車道を歩く。降りしきる雪の中、バスの出発にギリギリ間に合ったメンバーだけ先に帰ってもらった。残りのメンバーは屋根があるバスの待合場所で、向かいの豆腐屋で豆腐やドーナツ、ホット豆乳を購入するなどして、雪を見ながらバスを待った。
雪が降り始めるまでに下山すべく、やや忙しない山行になりましたが、皆さんのご協力で時間通りに完遂できたことを感謝いたします。 (神谷敏裕)
 養沢神社脇から 登山開始 |
 サルギ尾根の急登 |
 急登の後は急降下 |
 上高岩山からの 展望 |
 路面凍結で 四苦八苦 |
 大岳神社から 山頂へ |
 残雪が多い |
 展望のない山頂 |
 雪道を慎重に 下りる |
 雪を見ながら バスを待つ |
山行記録に戻る
13.高尾/小下沢ハナネコノメ鑑賞
期 日:3月15日(土) 日帰り 曇り
参加者:L安瀬はる江、SL杉江秀明、SL山口音子、矢澤孝二、助廣弘子、上野 進、黒澤壽子、近藤由美子、大貫文正、中村和江、伊藤和良、水内好江、中村公子、宮﨑博之、山崎 稔 計15名
コース:高尾駅北口9:52=バス=大下バス停10:20-休憩11:10~15-広場11:40~12:20-小下沢林道折返し点13:08-ザリクボルート入口13:25-ザリクボ滝13:50~14:05-広場14:30-大下バス停15:05(鑑賞時間50分含む)
当日の天気予報によると午後3時から小雨。そこで小下沢林道を往復。川沿いの花鑑賞に絞った。
時期外れの寒さで辺りはまだ冬の様相だった。木下沢梅園の梅は満開で大勢の人が散策していた。
歩き始めはホトケノザの群生。その中にタネツケバナ、ペンペンクサのお出迎いだった。ハナネコノメは川岸に咲いている。径が5ミリ程の小さな花で、上の林道からは探し難い。群生するので咲き進んでいるところは白い花が目立った。思いの他見つかり十分に鑑賞できた。蕾も多くこれから先も楽しめる。目当てのピンクやミドリの花は探せなかった。珍しいマメヅタ、タマゴケも発見。
帰りにザリクボルートを滝まで往復。ヨゴレネコノメソウ、ヤマネコノメソウ、ツルネコノメソウ、ハナネコノメ、フユイチゴ等も鑑賞できた。一輪薄いピンクのハナネコノメがあった。後はピッチを上げてバス停に。直前に雨がポツポツ。バス停が見えると走り始めたバスが止まり、全員駆け込み乗車できた。
メンバーの協調性が高く、足並みも揃い、順調に進めました。ありがとうございます。(安瀬はる江)
山行記録に戻る
14.秩父/城峯山
期 日:3月20日(木)日帰り 曇り時々晴れ
参加者:L萩原克己、SL神谷敏裕、SL岩月宣雄、上野進、大貫文正、金子盛次、延澤英明、岩井初江、要加月、黒澤寿子、支部外4名 計14名
コース:橋本駅7:00=西門平10:40-鍵掛城12:13~30-城峰山13:10~50-城峰神社14:10~20-西門平16:05=橋本駅
チャーターバスを利用し予定していた男衾登山口を目指すも、前日関東地方全域に降雪をもたらした影響で、コース変更を余儀なくさせられることとなった。
当初の下山予定だった西門平から10:40スタート。ここは関東ふれあいの道であり積雪はあるものの雪もしっかり付いていたので全員がツボ足で歩行(結局最後までツボ足)。鐘掛城(12:13)に到着し小休憩をとり城峯山を目指すも2つの峠(石間峠)がかなりの激下りと激登り、さらにノートレース状態(積雪は30cmから50㎝)ぐらいあり終始先頭を行く神谷さんは大変だったと思います。
城峯山(13:10)に到着しランチタイム、山頂電波塔展望台からの360度の眺望には圧巻。下山は城峯神社経由、雪化粧に包まれ凛とした空気に趣と風情を感じた。復路は峠を避け巻き道を利用したこともあり思ったよりもスムーズに西門平(16:05)下山することが出来た。
下山後のバスでは萩原Lの自家製果樹酒で乾杯。渋滞もさほどなく19時には橋本駅に到着。(岩月宣雄)
 登山口付近から 雪道 |
 鐘掛城に到着 |
 雪に埋もれた 階段を下りる |
 山頂の展望台が 見える |
 武甲山と 秩父の街並み |
 遠くに真っ白な 浅間山 |
 特徴的な山容の 両神山 |
 山頂にて |
 城峰神社にて |
 西門平登山口に 下りる |
山行記録に戻る
15.西丹沢/人遠尾根~ヒネゴ沢乗越
期 日:3月22日(土) 日帰り 晴れ
参加者:L松本悦栄、SL松宮俊彦、大貫文正、杉江秀明、矢澤孝二 、堤理恵子、高橋知美 計 7名
コース:新松田駅7:45=<バス>=湯本平バス停8:19~8:29―林道9:05―鉄塔9:32―湯本平分岐9:50―尾根下降地点9:58~10:07―人遠集落11:00―人遠尾根取付き11:10―622m辺り(昼食)12:05~12:30―657mピーク12:52―富士見台13:13~13:20―ヒネゴ沢乗越13:28~13:30―はなじょろ道入口14:08―田代向バス停15:08~15:40発乗車=<バス>新松田駅16:01
寒い日が続いていたが、当日は暖かな登山日和となった。今回は西丹沢を西から東へと進路を取り、山頂を目指すのではなく尾根にこだわったコースである。
新松田駅から発車するバスに乗車し湯本平バス停で降りたのは我々だけだった。バス停から少し戻り田中モーターズ会社への道を曲がりそのまま林道へと歩く。この林道はヘアピンカーブが多く2回ショートカットをした。林道の終点は大野山登り口で、尾根は広く歩きやすいうえ指導標があり道は明瞭だ。登ってきた尾根を振り返ると端正な姿の不老山。そして樹林の間から富士山が見えた。ここから50m弱で湯本平分岐に到着し林道に出た。すると猟師と思われる車両が20台ほど走り去った。休憩した後、林道を避けて645mのコブを越え下降点を探して、尾根の先端からジグザグに降りた。500mまでは急な下りで徐々に緩やかになるとミツマタが咲いていた。大野山の稜線をバックに集合写真を撮る。このまま尾根を外さないように下っていくと集落の近くまで来た。右寄りに歩くと明瞭な道に合流し人遠集落に降りた。民家の軒先には、ものすごい数の鹿の角がぶら下がっていて、10頭以上の猟犬が檻に入れられている。不審な7人を見た猟犬は歯を剥き出して吠える。目を合わせないよう素早く歩くが身が縮み上がる思いだった。
人遠橋を渡ると人遠尾根の取付き(約240m)の階段があり、急登の始まりである。450m辺りから間伐した木が放置され行く手を阻むが、尾根に光が入り明るいのが救いだ。途中、600m前後から南下(右側)するとホギリの山神があるようだが道はわからなかった。昼食後、150mほど登って富士見台で最後の展望を楽しんだ後は、トラバース道を歩いてヒネゴ沢乗越に向かった。一部崩れている箇所があり慎重に通過する。ヒネゴ沢乗越からは一般道のはなじょろ道になりゆるゆると降りて、中津川沿いの桜を見ながらバス停に向かった。
舗装道路で我々の横を軽トラが通りすぎた。その荷台には解体した後の肉と鹿の頭と角があった。
バリ好き・地図読み好きなメンバーが揃い、バリの魅力を大いに楽しんだ一日だった。(松本悦栄)
山行記録に戻る
16.町田/七国山周辺ハイキング
期 日: 3月30日(日) 日帰り、晴れ
参加者:L神谷友子、矢澤孝二、助廣弘子、SL佐藤邦弘、神谷敏裕、金子盛次、岩井初江、要加月、山﨑稔、山﨑龍子(支部外) 計10名
コース:市立博物館前バス停9:30―本町田遺跡公園9:20―町田薬師池公園10:00―七国山11:20―四季彩の杜西園12:05
花冷えの中、前日の雨が上がり昨年のリベンジに向かう。トイレに立ち寄った本町田遺跡公園で竪穴式住居を見学し、せせらぎが続く“なかよし散歩道”とロードを歩き薬師池公園まで。
途中には、土筆、ムサシアブミ、野草園ではカタクリ、イチリンソウ、シャクヤク、ヒゴスミレなど様々な春の草花と出会った(ようだ)が、知識不足と目的地にたどり着きたい気持ちが優先し、愛でる余裕はあまりなかった。
鎌倉古道の先にある七国山の頂上は、以前は雑木林で入れなかったが今は伐採され三角点にもタッチできた。今回の目的のひとつである一面の菜の花畑は時期尚早で残念。しかしサブリーダーが教えてくれた(前日下見まで)ダリア園にある見事な満開の桜の木のもとで最高の記念撮影ができた。無事西薗のゲートに到着し午後は自由解散とした。(神谷友子)
山行記録に戻る
17.多摩丘陵/二ヶ領用水~緑ヶ丘霊園~東高根森林公園
期 日:4月3日(木) 日帰り 小雨
参加者:L佐藤邦弘、大貫文正 計2名
コース:小田急線登戸駅10:06―多摩川土手―二ヶ領用水宿河原堀10:24―新船島橋10:29―南武線下10:34―北村橋10:40―宿河原橋10:47―緑10:50―八幡下橋10:59―みどりの吊り橋11:03―緑化センター あずまや11:10―宿之島橋11:22―たか橋11:23―稲荷神社11:28―東名高速道路下11:30―新明橋―JR南武線久地駅11:37
4月2日(水)の予定は悪天候が見込まれたため、翌3日に延期しての実施となる。3日もまた雨の可能性は予想されたが、良いほうに転ぶことを期待して決行した。弱い雨が降るなか、登戸駅から傘をさして歩き出す。たいした雨ではない。行動中はこの程度の雨であることを念じつつ、多摩川の土手にあがり、桜並木が続く二ヶ領用水宿河原堀に向かった。
満開の桜(ソメイヨシノ)が目の前に広がり、思わず感嘆の声。多摩川から引き込まれた用水が流れ、その両岸は淡いピンク色の桜花が咲き乱れて、圧巻の一言。雨のせいか、花見客はまばらで、人の賑わいはなく、野鳥の鳴き声が響く、静かな空間だ。用水に接して歩道用の木製デッキが設置され、飛び石なども配置されて、風情がある。電車が通る南武線の下を腰をかがめて、くぐり抜ける箇所もあってなんともおもしろい。小雨に濡れた桜花もまた乙なものだ。桜花爛漫の空間をゆっくり歩いて、1時間程度が経ったころ、東名高速道路にぶつかる。この手前で二ヶ領用水宿河原堀の桜並木は途切れた。そして、巨大なコンクリートの東名高速道路下を通り抜け、ほどなくして神明橋を渡るとJR南武線久地駅に出た。
予定のゴールはまだ先であったが、小雨と帰路の交通の便も勘案し、メインの二ヶ領用水宿河原堀の桜を満喫したことで、予定を変更して、久地駅で打ち切りとした。コースを短縮したが、思いがけない静かな花見となり、これがまたいささか得したような気分にさせた。加えて、川崎の多摩川近くに引っ越してきた10歳ごろのことが思い出され、真っ黒で異臭を放つ汚水が流れていた多摩川が、今や再生し、好ましい自然環境を形づくっていることに感慨深いものがあった。(佐藤邦弘)
土手から 多摩川橋梁を見る |
ニヶ領用水 宿河原堀の桜 |
ニヶ領用水 宿河原堀の桜 |
ニヶ領用水 宿河原堀の桜 |
ニヶ領用水 宿河原堀の桜 |
ニヶ領用水 宿河原堀の桜 |
ニヶ領用水 宿河原堀の桜 |
ニヶ領用水 宿河原堀の桜 |
ニヶ領用水 宿河原堀の桜 |
正一位稲荷大明神 |
山行記録に戻る
18.四国/剣山、飯野山
期 日: 4月3日(木)~5日(土) 前夜発二泊三日 晴れ
参加者:L萩原克己、SL神谷敏裕、矢澤孝二、岩月宣雄、神谷和男、(支部外) 計6名
コース:横浜駅YCAT22:15=徳島駅6:35~7:35=阿波池田駅9:45~10:25=久保12:30~45=見ノ越13:55(剱神社 泊)~7:00-西島駅7:50~55-次郎笈9:30~50-剣山11:15~40-二ノ森12:35~50-剣山頂ヒュッテ13:35~40-西島駅14:15~25-見ノ越15:00~25=京上16:15(奥祖谷 泊)~7:48=阿波池田駅9:26~10:23=丸亀駅11:03~15=飯山町登山口11:35~40-飯野山(讃岐富士)12:30~55-野外活動センター13:55~14:00=丸亀駅14:20
費 用:横浜駅YCAT=徳島駅(コトバス)7,900円、阿波池田駅=久保(四国交通バス)1,790円
久保=見ノ越=京上(三嶺タクシー)10,110円+11,280円、京上=阿波池田駅(四国交通バス)1,580円
丸亀駅=飯山町登山口、野外活動センター=丸亀駅(丸亀タクシー)3,150円+2,610円
剱神社簡易宿泊所(2食付き)8,000円、旅の宿奥祖谷(2食付き)10,450円
四国剣山は平家伝説の残る祖谷の奥に聳える西日本第二の高峰である。安徳天皇が再興を祈念して剣を埋めたとの故事が山名の由来で、深田百名山にも選ばれている。
その登山口である見ノ越へは1日がかりだ。徳島駅で参加者が集合、JRとバスを乗り継いで吉野川から祖谷に入って行く。辺りは峡谷が狭まり、ほとんど平地が見られない。山の斜面にミツマタが咲いているが、今でも重要な産業のようだ。
バス終点でタクシーに乗り換え、途中でかずら橋を見学し見ノ越に着く。ここから登山リフトが架かっているが、4月下旬からの運行なので、今は閑散としている。剱神社が祀られており、社殿の脇に簡易宿泊所がある。泊りは我々だけ。さっそく風呂に入って夕食をいただく。つい最近まで、ここでも1㍍の雪が残っていたそうだ。
翌登山日は快晴に明ける。朝食を6時にしてもらって7時には出発。宿泊所の横が登山口だ。樹林帯を登って行くと、次第に残雪が現れる。リフト西島駅下のキャンプ指定地で樹林が途切れると、青空の下、次郎笈と三嶺がすっきりと望まれた。そして、何よりも霧氷。まだ芽吹き前の枝々すべてに咲いた氷の華が、朝日にきらきら輝いている。
巻き道を通ってまずは次郎笈へ。山頂は風が強く、四国でもさすがに2千㍍近い稜線は、まだ冬の空気が支配的だ。しかし陽光は確実に春を感じさせる。見渡す山々の、まだ薄い灰色の山肌と残雪そして稜線近くの霧氷は薄ピンクに見え、まるで満開の桜を遠くから眺めているようだった。
稜線を戻って剣山の本峰に到着。山頂付近は植生保護で板敷になっており、三角点も囲いの中だった。剱神社の奥社が祀られ、直下にはヒュッテもあるがリフト同様営業前なので、まだ登山者は少ない。ここからの次郎笈も立派で、山容自体は本峰(太郎笈)よりも優れているなとは、メンバー全員の一致した意見だった。しかし東西南北、見渡す限りの山並みだ。遥か南に海のような輝きが見られたが、果たして太平洋だろうか?
続いて東の一の森へと脚を延ばす。山頂からは次郎笈、三嶺そして剣山本峰が並んで眺められ、いつか三嶺そしてその先への縦走に夢を描いたのだった。
下りは山頂北側に多くの残雪があったが、もう一部だけ。霧氷もあらかた溶け落ちて、西島駅で登りのルートに合流し、見の越に下山した。神社の宿泊所でお茶をいただき休憩後、タクシーで奥祖谷の民宿へ向かう。夕食は鹿肉や山菜など、山の宿に相応しい豪華なものだった。
3日目、朝食後バスで池田駅に戻り、丸亀に向かう。今日の登山は讃岐富士とも呼ばれる飯野山だ。タクシーで桃の花咲く登山口から階段状で一気の登りとなる。八合目で下山路に使う、鉢巻状に登る道に合流し山頂へ。薬師堂を中心に広い山頂には桜が舞い、地元の方々が大勢お弁当を広げていた。展望台から溜池の多い讃岐平野や瀬戸内海を眺め、さあ下ろう。登山口のビジターセンターで登山証明書のカードをいただき、往きと同じタクシーで丸亀駅に戻った。
剣山と讃岐富士、違ったタイプの楽しい山旅だった。(矢澤孝二)
山行記録に戻る
19.長野/霧訪山(1305.7m)(花山行)
期 日:4月20日(日) 日帰り 晴れ
参加者:L安瀬はる江、SL油田まり子、大貫文正、繁村純夫、繁村美知子、大槻章夫 計6名
コース:塩尻駅9:40=タクシー=たまらずの池10:00―1025m鉄塔10:50―霧訪山山頂11:50~12:30―1196m12:50―大芝山13:35~40―洞の峰1199m14:00―950m鉄塔14:10~15―山の神自然園14:45~15:00―塩尻駅16:10 タクシー料金850円/一人
杞憂した当日の天候は薄陽が射すほどだった。霧訪山は山名に魅かれる。長野県里山の一番人気だと聞く。花の種類も多く、山頂のオキナグサは特に名高い。
出発はたまらずの池。斜面一面の福寿草の花は終わり、葉が伸びていた。他の花も2,3種あった。1025m鉄塔までは急登だが、つづらで淡々と熟す。途中のイワウチワには元気をもらった。足を止め振り返ると、まだ芽吹かない林の中に白いタムシバが目立つ。1ヶ月程春が浅い。歩を進めていくとカタクリがちらほらと咲く。山頂手前で女坂と男坂に分かれるが、男坂は一直線の急登で敬遠した。
山頂は草原状の小ピークで大勢の登山者がいた。オキナグサの株は激減して、とても小さい姿で、2輪が半開していた。山頂からの展望も360度で圧巻。高嶺は雲がかかっていたが山座同定ができた。特に八ヶ岳方面ははっきりしていた。
大芝山に向かって下山する。スミレが多くなり、観察に忙しい。群生するはずのニリンソウはまだ葉がでたばかりだった。ここでは登りとは違う花を楽しめた。洞の峰からは塩尻の市街地が望めた。
降り立った林道の土手にはスミレが満開。よく見るといろいろな種類が見つかり、時間が足りなかった。最後にタクシーが混んでいて、塩尻駅まで1時間歩行を余儀なくされた。
山行中の花々、イチリンソウ、イワボタン、ヒゲネワチガイソウ、キバナノアマナ、ミヤマカタバミ、ツルリンドウ葉、ミヤウズラ葉、イワウチワ、カタクリ、オキナグサ、ミヤマウグイスカグラ、ヤマエンゴサク、ユキザサ蕾、アブラチャン、レンプクソウ、アカフタチツボスミレ、アメリカスミレサイシン、マルバスミレ、ヒカゲスミレ、ケタチツボスミレ、マキノスミレ、フイリシハイマキノスミレ、イブキスミレ、エイザンスミレ、ヒナスミレ、タムシバ等(安瀬はる江)
山行記録に戻る
20.町田えびね園から薬師池公園
期 日:4月25日(金)日帰り 曇りのち晴れ
参加者:L若松節子、SL佐藤邦弘、助廣弘子、大槻章夫、大貫文正、榎本美智子、山崎好子、中村博雄、竹田早苗、黒澤壽子、支部外 平山今紀江 計11名
コース:町田駅バスターミナル9:52=藤が丘団地―10:10~11:30えびね園―11:40~12:30薬師池公園―薬師堂―13:10~13:45ぼたん園―七国山雑木林―14:20山崎団地給水塔前バス停
藤が丘団地入口バス停よりえびね園に入る。緩やかに雑木林の中を下り始めるがもうそここに目的のエビネが顔をみせる。春の山野草たちに出迎えられ皆足が進まない。ゆっくりと写真を撮りながら園内を一周。鎌倉街道を渡り薬師池公園へ。
鮮やかな新緑の中藤棚の下で昼食。採れたてのタケノコをゲットし薬師堂に向かう。町田の市街地を眺めながら花探し。途中の民家の庭先の珍しい深いローズ色の花の名前を住人の方に教えた頂く。外来種のクロバナロウバイだそうだ。
ボタン園に向かう手前の民家にセッコクの花が咲いているというので、お庭にお邪魔させて頂き写真タイム。目の高さのセッコクは迫力満点。真っ黄色の菜の花畑を見ながら歩を進める。ボタン園はボタンをはじめシャクヤク、つつじ、御衣黄桜まで見ることができた。
ここで3名の方が時間切れになりお別れ。歩き足りないメンバーは七国山の雑木林を横切り山崎団地のバス停に向かう。
佐藤SLのご案内で楽しい1日を過ごせました。
ツタバウンラン、キンラン、ギンラン、各種エビネ、シラユキケシ、ウラシマソウ、ムサシアブミ、クマガイソウ、ユキモチソウ、コバノタツナミソウ、白花タツナミソウ等々 まだまだいろいろな花たちが咲き誇っていましたが書ききれません。(若松節子)
 えびね苑に咲く キエビネ |
 えびね苑の タカネエビネ |
 えびね苑の ジュウニヒトエ |
 えびね苑の クマガイソウ |
 薬師池公園の 藤棚の下で |
 次はぼたん園へ |
 民家の セッコクの花 |
 菜の花畑の前で |
 ぼたん園から 七国山緑地へ |
 七国山緑地の 散策路 |
山行記録に戻る
21.野坂岳山系・赤坂山山系/野坂岳~赤坂
期 日:4月25日(金)~26日(土) 一泊二日 晴れのち曇り/晴れのち曇り
参加者:L松本悦栄、SL矢澤孝二、松宮俊彦、小磯登志子、堤理恵子 計 5名
コース:
一日目 敦賀駅12:30=<タクシー>=野坂岳登山口12:50~13:02―橡の木地蔵13:39~13:59―行者岩
14:29~14:34―一の岳14:44 ~14:50―二の岳15:12―三の岳15:26―野坂岳山頂避難小屋
15:37―野坂岳15:38~15:44―野坂岳山頂避難小屋(泊)
二日目 野坂岳山頂難小屋5:26―野坂岳5:26~5:32―山ルート分岐6:24―茶屋谷山6:39―芦谷山8:
01~8:02―新庄乗越9:10~9:31―三国山11:35~11:56(昼食)―三国山分岐12:09~12:12
―明王ノ禿12:38~12:44―赤坂山13:16~13:19―栗柄越13:31―鉄塔基部広場13:34―赤
坂山・三国山登山口14:49―マキノ高原温泉さらさバス停15:04~15:13
新横浜駅から関西へ向かうと電車時刻が乱れていたが途中駅で合流し、敦賀駅からはうまい具合に大型タクシーで野坂岳登山口までお願いをした。
登山口から歩き出して橡の木地蔵で明日の分までの水を汲んだ。途中で行者岩があったのでそちらへ向かうと西側方面の展望が見えた。戻って行くと斜面には雪が残っていて風が吹くと寒いがブナの芽吹きも見れた。避難小屋に着き野坂岳は直ぐそこである。今夜は私達だけだった。
翌日の5時26分に歩き出し野坂岳山頂へ行く。今日も寒いなぁ。南方面に向かうと、エフがあり山ルート分岐までは歩きやすい道だった。茶屋谷山や芦谷山を越えてきたがまだ薄い道はあった。イワウチワが出てきたりしたが日差しが欲しいところだ。新庄乗越からは雪や倒木などがあり焦らずじっくりと歩く。やっとのことで三国山について昼食にした。登山者がいてこれからは楽に歩けると思ったがまだまだ先は長い。明王ノ禿に着くと奇岩が沢山あった。お花も多く関西の山の雰囲気が味わえた。休憩をした後、琵琶湖を望みながら歩を進めていくと赤坂山に着いたが、その後の登山口までが長かった。そしてあと少しでマキノ高原温泉バス停だった。
野坂岳からの道はやはり大変だったが、参加の皆様のご協力を得られて無事登り終えることが出来ました。ありがとうございました。 (松本悦栄)
 いよいよ出発 |
 オオカメノキ |
 イワウチワ |
 三国山 |
 明王ノ禿の奇岩 |
 赤坂山 |
 マキノ高原温泉 まで来た! |
山行記録に戻る
22.三浦半島/葉山公園~峯山~子安の里
期 日:4月29日(火・祝) 日帰り 晴
参加者:L佐藤邦弘、SL大貫文正、森田隆仁、榎本美智子、助廣弘子、上野 進、黒澤寿子、杉江秀明、堤 理恵子、若松節子、英賀昇子、太田久枝、中村公子、山崎 稔 計14名
コース:JR逗子駅9:41=葉山バス停10:05―神奈川県立葉山公園10:10―峯山大池分岐―峯山大池11:30―峯山大池分岐―峯山―子安の里分岐付近(昼食)12:07~30―光雲寺―関根川―新子安橋―西行院(さいこういん)―庚申塔群―子安道(古道)―倒木(進路を阻まれ、往路を戻る)13:45~14:00―関根川遊歩道―新子安橋―関根不動尊―久留和バス停14:55=JR逗子駅15:35
空は晴れて4月にしては陽射しが強く、汗ばむ陽気。御用邸を囲む塀沿いを歩いて葉山公園に着くと、目の前の海にはヨットが浮かび、カヌーに興じる人がたくさん。これが湘南の風景か。霊峰富士は雲隠れとは残念。
住宅が並ぶ峯山への入口は迷ってウロウロしたが、地図読みの達人が参加しているのでなんとも心強い。急坂の舗装路を上がっていくと眼下に相模湾が広がり、伊豆半島、箱根の山々が見えて絶景のロケーションだ。一本の細い山道に変わり、慎重に高度を上げる。この付近は「大崩」という怖い地名が記されている。かつてがけ崩れが起きたのだろう。しばらく歩くと舗装路に変化。眺望の素晴らしい高台に豪華な家が点在している。空と海が青く輝いて広がり、真っ白いかたまりの雲がポカンと浮かぶ。山は新緑真っ盛り。草花は色とりどりに咲いて、まさに春爛漫の丘だ。
鬱蒼とした山中へと続く踏み跡。ぬかるんで滑りやすい密林の山道を降れば、窪地に池が出現。ここが峯山の大池。わずかながら水を湛えて静かに横たわっていた。そびえたつ秋谷の配水塔を過ぎて、草が刈られた場所で昼食。その後、子安へと続く山道へ。道は明瞭。捨てられてタケノコの皮が目に付く。広々と開けて大楠山や湘南国際村を遠望する展望地に出た。斜面の草原にオスの雉(キジ)を見る。ここから子安の里はもう少しだ。
子安の里の庚申塔群を見て、昔、秋谷と子安を結んでいたという山越えの子安道に入る。入口はわかりづらいが、道は意外と明瞭で古道の雰囲気を感じながら進む。が、前方に大木が倒れていて道を塞いでいる。慎重に状況確認の末、この障害物を越えるには危険が大きく、無念のリターンとなった。
予想外のコース変更となったが、幸運にも親切な地元の方に出くわし、渓谷的雰囲気を醸す関根川遊歩道を教えてもらい、心地よい疲れを覚えながら、久留和バス停に向かった。(佐藤邦弘)
山行記録に戻る
23.奥多摩/御前山
期 日:4月30日(水) 快晴
参加者:L神谷敏裕、伊藤和良、延澤英明、要 加月、瀧沢正明 計5名
コース:奥多摩駅7:40=奥多摩湖7:55~8:05-サス沢山9:20~9:28-惣岳山10:43~10:55-御前山11:20~11:48-トチノキ広場13:00~13:06-寄森の家13:44-境橋14:35~14:40-奥多摩駅15:35
8:07発のバス乗車を予定していたが、早めに全員集合できたので7:40発の鴨沢西行バスに乗車。平日ではあるがGW中のため登山客が多く臨時バスが出た。
奥多摩湖畔で身支度し、小河内ダムの上を渡って登山道に入る。大ブナ尾根を登っていくが、サス沢山までは上りが続く。サス沢山からは快晴でブルーに染まった奥多摩湖が直下に見え、遠方には大菩薩嶺が望める。1230m辺りから広葉樹を中心とした植生に代わり、ハルリンドウ、スミレなどの花が現れる。惣岳山に近づくと、今回目的のカタクリの花が徐々に表れる。カタクリは7年経たないと開花しないそうで、カタクリの葉は多くみられるが花はポツポツと咲いている感じ。カタクリは御前山周辺まで咲いており、山頂直下の柵の奥は群生して咲いていた。
下山は栃寄に向けて下りていく。登山道がいくつも枝分かれしていて分かりづらいが、活動の広場を目指して歩く。やがて山道は林道となりトチノキ広場に至る。本来は栃寄沢沿いの山道を歩くと距離が短いが、山道崩壊で通行止めとなっており延々と車道を歩く。栃寄森の家や放流用ヤマメを育てている氷川養魚池、草花等を眺めながら境橋バス停まで歩いて行く。
バス停で時間を見ると次の発車まで1時間以上ある。待っていても何もすることがないので、奥多摩駅まで歩くことに。橋のたもとから「奥多摩むかし道」に入る。民家が点在する道。途中、道の先にカモシカも目撃。予定より約1時間余計に歩いて奥多摩駅に到着。電車の発車まで30分ほど時間があったので、駅の2階で喉を潤して帰宅した。 (神谷敏裕)
山行記録に戻る
24.郡内/扇山
期 日:5月3日(土・祝) 日帰り 晴れ
参加者:L安瀬はる江、SL堤 理恵子、大貫文正、山口音子、水内好江、黒川恵理子、黒澤壽子、助廣弘子、高原春子(支部外)(計9名)
コース:鳥沢駅9:00=バス=梨の木平バス停9:15―ツツジコース登山口9:25―820m10:00~05―稜線10:55~11:00―扇山山頂11:10~12:05―山谷分岐12:35―恋塚分岐13:30~35―犬目14:00ー大田峠14:50―梁川駅15:27~48
我が故郷の山、扇山。ツツジコースが紹介され、花時に再訪を願っていた。
鳥沢駅前バス停は20号沿いで長蛇の列ができ、満員だった。今回、ヤマツツジは満開で登山道の両脇に、
そしてトンネル状にと、オレンジ色の花で埋まっていた。登山道はつづらの急登で、前日の雨も手伝って足を取られる所もあった。途中の樹間からは富士山がくっきりと望めた。
本道分岐に合流するとちらほら馴染みの花が目立つ。青空を背に新緑が一層映えた場所だった。稜線にでて、一休み。緩やかに登っていくと、広い山頂には大勢の登山者がいた。車座になれる場所で、手早くできた豚汁を囲みゆっくりと団欒した。清々しい空気もご馳走だった。
下山始めて山谷分岐の先で、ゲストさんに貴重な花、ルイヨウボタンの群生地を案内して頂いた。稀にみる多量な株で、花は見頃だった。犬目の集落までは歩き易い一般道で種々の花に出あえた。ゴルフ場脇の舗装道に出ると藤の花があちこち盛りで、元気をもらい大田集落まで頑張る。大田から梁川駅までは地図読みして、細い山道を辿った。唯一大田峠には私製の道標が立木にかかっていた。
山行中の花々、ヤマツツジ、ツチグリ、ヒトリシズカ、フタリシズカ、ミミガタテンナンショウ、タチツボスミレ、ルイヨウボタン、チゴユリ、フデリンドウ、イカリソウ、ジュウニヒトエ、フジ、キツネアザミ、セリバヒエンソウ、クゲヌマラン、ギンラン、ホタルカズラ等(安瀬はる江)
山行記録に戻る
25.鎌倉/市境尾根~荒井沢市民の森~六国見山
期 日:5月13日(火) 日帰り 晴
参加者:L佐藤邦弘、SL杉江秀明、助廣弘子、上野 進、黒澤寿子、武末範子、瀧沢正明、中村博雄 計8名
コース:JR大船駅9:35―砂押橋交差点10:03―大長寺10:10―市境尾根10:20―公田の住宅地―市境尾根―散在ヶ池分岐― 荒井沢市民の森―皆城山展望台(昼食)11:50~12:20―谷戸田の池(湿地)―極楽広場―墓地―市境尾根―今泉一丁目―岩瀬中学校―大船高野配水池―六国見山展望台13:55~14:15―好好洞14:40―JR北鎌倉駅臨時口14:45
古い街並みと新しい街並みが雑然とした大船駅東側の風景。落着きがないかわりに人の流れが活気を生んでいるように映る。駅前に砂押川が流れ、川沿いの桜並木の道を歩いて大長寺を目指す。
途中、老婦人がこの近くに松竹大船撮影所があって、俳優をよく見かけたと懐かしむように話していた。
大長寺の高台の墓が終わるところから、こころ細い山道が奥に続いている。道標は見当たらない。しばらく狭い尾根道。急下降の箇所が二ヶ所現れる。いずれも太いロープがあり、大いに役立った。一旦、尾根から離れ、横浜市公田の住宅地を抜けて、再び市境尾根に復帰。30人の山の会グループに遭遇。
5月半ばだが、山の緑はすでに濃い。爽やかな新緑の季節は過ぎたようだが、色とりどりの山野草の花が豊富だ。市境尾根付近の谷戸は畑が発達し、利用されている。散在ガ池分岐を過ぎ、荒井沢市民の森へと入り、皆城山展望台に着く。表示板によると富士山や丹沢山塊をはじめとして奥多摩などが遠望できるようだが、木の葉が茂り、見晴らし悪く、なんとか横浜のランドマークタワーを確認。展望台から少し戻り、タツナミ草の群生を見ながら長い階段を降ると谷戸(湿地)に降り立つ。気持ちの良い谷戸田の風景が広がるなかを行く。
荒井沢市民の森を出て周辺を見渡すと、地層が剥き出しとなった恐ろしいほどの断崖が目に飛び込む。「横浜のグランドキャニオン」という愛称があるというが、驚きだ。帰宅後、ネットで調べてみると、1965 年頃東名高速道路の建設に伴って、山砂採取のために山が削られ出現した断崖だという。これも高度経済成長期の遺物ということか。
市境尾根から道標もない迷路のような山道を辿って麓の鎌倉市今泉の住宅地に降りる。砂押川を渡り、六国見山展望台を目指して登り返さなければならない。急な階段を越え、ようやく六国見山展望台へと続く尾根に。
六国見山展望台から相模湾を望むが、視界は不良。ゆっくりと休憩し、展望台を後にする。北鎌倉駅へ向かう途中の高台から真っ白く大きな大船観音の姿。崖の付近に建つ家々見て、横須賀線の踏み切り手前を曲がる。好好洞という岩をくり抜いた素掘りのトンネルを抜けると北鎌倉駅臨時口はすぐだった。(佐藤邦弘)
山行記録に戻る
26.富士山自然休養林
期日:5月22日(木)日帰り 曇り時々晴
参加者:L若松節子、SL安瀬はる江、SL堤理恵子、助廣弘子、大貫文正、大槻章夫、繫村美知子、黒澤壽子、杉江秀明、榎本美智子、武末範子、中村和江、宮崎博之、中村博雄、
支部外:高原春子、小野とも子、中島美千代 計17名
コース:八王子駅南口6;55=水が塚公園9;00―お胎内下山道分岐10;30―幕岩下11;00~11;45―お胎内下山口13:00=八王子駅南口
前日までの天気予報は朝から雨模様。いちかばちかで雨具を用意して出発。どんよりと曇っているが雨の気配は無し。
水が塚公園で自己紹介の後出発。早速アシタカツツジが咲いている。お目当ての一つはハイキングコース入口のヤマトグサだが時期が遅かったためか見つけることができずじまい。
東国ミツバツツジが緑の中一際美しい。花博士が足元の小さな花を案内して下さる。脚は進まず気が付くとコースタイム20分のところ1時間もかかっていた。
今日一番の目的のヤマシャクヤクを探しに下山道分岐に。残念つぼみばかり。なんとなく皆さんの視線が・・・
気を取り直し昨年見つけた幕岩下の群落地に向かう。良かったー咲いていた。可憐なヤマシャクヤクの撮影会。昼食後ゆっくりお胎内下山道を下りお胎内神社の溶岩流跡を数人の方がくぐる。頭をぶつけた人もいましたね。
ご参加皆様の協力に感謝致します。(若松節子)
山行記録に戻る
27.谷川連峰/平標山~仙ノ倉山
期 日:5月30日(金) 小雨のち曇り
参加者:L神谷敏裕、山口音子、中村和江 計3名
コース:越後湯沢駅8:20=平標登山口8:54~9:00-松手山10:55~11:05-平標山12:35~12:55-仙ノ倉山13:05~14:05-平標山14:55~15:15-平標山乃家16:00~16:10-登山口17:05-平標登山口18:05~18:10-元橋バス停18:15~18:26=18:58越後湯沢駅
当初計画では越後湯沢に前泊し土曜日に登る予定にしていたが、週末は低気圧の接近で天気が崩れる予報。ただ金曜日は朝のうちは雨予報だがその後はほとんど降らないと判断し、1日前倒して実施。
バスで平標登山口に到着すると小雨。濡れた山道を慎重に登る。1時間ほど歩き1411m近くの鉄塔まで来ると雨が止む。更に進むと松手山付近からはマメザクラ、イワナシなどの花が増える。遠くには苗場スキー場や苗場山などが望める。平標山頂手前のハクサンイチゲ群落は見事。シャクナゲも山頂周辺を中心に薄いピンク色の花が咲き始めている。
平標山頂あたりまで来るとガスが立ち込め遠方が見えなくなる。仙ノ倉山に進むと色の濃いハクサンコザクラやミヤマキンバイなどが散見され、更に先には背の低いマメザクラが増える。雪の重みでそうなるのだろうが、手入れをしたような見事な枝ぶり。仙ノ倉山頂に来ると一旦ガスが切れ、苗場山方面や万太郎山が望めた。
平標山に引き返し、今度は平標山乃家に向かって下りていく。今年は積雪が多かったため雪渓が残り慎重に進む。また木の階段は雪でかなり崩壊しており歩きにくい。この辺りはショウジョウバカマが群生。
平標山乃家で少し休み、更に平元新道を下っていく。登山口まで下りると沢沿いに距離のある林道となる。途中からはまた山道に入り暫く歩くと平標登山口に帰着。更に元橋バス停まで歩くと間もなくバスが到着。梅雨直前の低気圧に翻弄されたが、ほとんど雨に降られず実施できて良かった。(神谷敏裕)
 順調に上る |
 山頂に近づく |
 苗場山方面を バックに |
 ハクサンイチゲが群生 |
 マメザクラが満開 |
 平標山頂にて |
 仙ノ倉山頂 |
 色の濃い ハクサンコザクラ |
 ショウジョウバカマが群落 |
 イワナシの花が 多い |
山行記録に戻る
28.みちのく潮風トレイルパート5
期 日:6月4日(水)~6日(金) 二泊三日 各日共に晴天
参加者:L若松節子、SL堤理恵子、SL後藤勝弘、大貫文正、大槻章夫、岩井初江、伊藤有子、上野 進、杉江秀明、横川芳江、萩原克己、支部外高原春子 計12名
コース;
6月4日 仙台駅仙北ライン10:18=石巻11:16―羽黒山神社13:20―日和山公園13:30~14:00―旧門脇小学校―石巻元気市場14:45~15:30-石巻サンプラザホテル15:45
6月5日 ホテル出発8:00―網地島ライン乗船9:00~田代島大泊港9:36―猫神社10:00―三石観音10:45~11:10―漫画アイランド11:50~12:20ー仁戸田港12:45~13:34=網地島網地港13:55―トレイル分岐14:36―長渡港15:40~鮎川港16:50=民宿めぐろ17:10
6月6日 民宿7:50=鮎川港8:10~8:40金華山港9:00―黄金山神社―水神社9:45―稜線分岐―10:00山頂10:15~10:30-二の御殿10:55―造林小屋11:20―黄金山神社12:00―金華山港12:20~12:45=鮎川港14:30=石巻駅15:30
6月4日 仙台駅仙北ライン車中で11名合流。お一人連絡がうまくいかずに先に石巻駅へ。駅前にてめいめい昼食をとりかわみなとコースの羽黒山神社に向かう。見上げる長い石段が待っている。登り切ると太平洋が広々と広がり歓声をあげながら日和山公園に向かう。ここは桜の名所との事、日和山神社に向かう。旧北上川が左手に流れ展望を楽しむ。先ほどの羽黒山もここ日和山も東日本大震災の時多くの方々がここに避難されて辛く寒い思いをされた場所だそうです。坂を下りると震災遺構の旧門脇小学校の無残な様子を見つつ翌日の乗船場を確認するため北上川の土手を歩く。
6月5日 乗船手続き等時間にゆとりを見て早めに船着き場へ。波に揺られながら田代島へ上陸。猫島の異名の通り下船後すぐに猫たちに迎えられる。
野生のミョウガが一杯の簡易舗装の道を息咳き入って上り詰めると猫神社。守り神の様に2匹の猫が餌をねだる。
やがて太平洋が見えてきて道も平坦になる。島の最高峰でも100mに満たない島。遠くの石巻市を眺めつつ歩を進めるとあちらこちらにカンゾウの黄色な花が咲き誇る。
三石観音の分岐からトレイルを離れ観音様に拝礼。三石広場で休憩のち漫画アイランドという宿泊施設の庭をお借りして昼食。港に向かうが時間の配分が判らず早めに港に到着。のんびり潮風に吹かれながら次のフェリーを待つ。無事に網地島上陸。地元の方にトレイルの入り口を伺い竹藪の中の道をたどる。所々にサイハイラン。
島を貫くアスファルト道をたどる。途中トレイルの分岐を見るが船の乗船時間が心配なのでそのまま村道を行く。2島共時間を気にしつつ早めに港に着きのんびりする。
(民宿めぐろは震災で建物に被害を受け再建されたとの事。新しくてきれいでした。料理の豪華で美味しいこと、但し予約時より値上っていました。)
6月6日 都合で一人先に帰京するH氏と別れ鮎川港へ。予約の海上タクシーにて金華山へ。神社に参拝の後沢通しの登山道を歩き始めからお目当てのベニバナヤマシャクヤクが迎えてくれる。九輪草が種を抱きながらあちらこちらに。山頂の先の広場で長めの休憩後下山。芝生の登山道で歩きやすい。暫く歩くとヤマシャクの大群落。
所々に白花も混じっている。花の見ごろにぴったりと合いみなで喜ぶ。午後から波が立ち船が揺れやすくなるので早めに下山したほうが良いとの海上タクシーのスタッフの方の助言に従い港へ。鮎川港に戻り昼食とのどを潤して石巻行のバスを待つ。
みちのく潮風トレイルを歩く際、毎回ですが実踏せずに本番を迎えます。東北の交通機関の時間選びの難しさと今回は船便に乗り遅れると島に取り残される不安で行動が早め早めになり結果港での長休憩になってしまったことをご参加の皆様にはお詫び申し上げます。いつも適切な判断をして頂けるSLのお二方と協力的なご参加の皆様に深く感謝申し上げます。(若松節子)
山行記録に戻る
29.八ヶ岳/にゅう
期 日:6月13日(金)~14日(土) 曇り時々晴れ
参加者:L神谷敏裕、堤理恵子、中村和江 計3名
コース:
13日 町田駅6:30=麦草峠9:40~10:00-青苔荘10:37~10:45-にゅう12:15~12:45-にゅう分岐14:07~14:17-中山14:30-高見石小屋15:40~15:50-白駒荘16:02-青苔荘16:35
14日 青苔荘7:40-麦草峠8:20~8:30=町田駅14:10 (御射鹿池に立ち寄り)
費 用 青苔荘 9,900円(1泊2食、モンベル割500円)
計画は13日にテント泊、14日ににゅう登山を予定していたが、14日が雨予報のためテント泊をあきらめて小屋泊、にゅう登山は13日に変更して実施。町田駅を自家用車で出発。
麦草峠に到着時、駐車場は8割の入り。薄曇りの中、準備を整えて出発。峠近くの茶臼岳もはっきり見える。暫く歩くと富士山五合目の奥庭を小型にしたような奥庭が現れる。白駒池入口には有料駐車場があり白駒池までが観光地となっているため、周辺は立派な木道が整備されている。青苔荘に立ち寄って不要な荷物を預け、湖畔を時計回りに歩く。湖畔を離れて暫く行くと白駒湿原。この辺りの山道は悪路で、所々は森の中をトラバースしながら進む。
にゅう山頂への最後は約200mを一気に登る。にゅうのトップからは間近に稲子岳、南側に東天狗、西天狗、北西側に北横岳、蓼科山などが望める。にゅうからは切り立った崖に沿って歩く。途中、稲子岳へのルートを20分ほど探したが明らかな踏み後は見つからず、おそらくここが入口だろうという場所のみ確認した。にゅう分岐からは北上方向にルートをとり中山へ。ガスが殆どなくなり硫黄岳がはっきりと見える。また逆側には蓼科山の山容が確認できる。中山展望台を過ぎると、岩がころがる山道をひたすら下っていく。高見石小屋で暫く休憩。更に30分ほど下ると白駒池湖畔の白駒荘へ。この山荘は建て増しをしたようで、建物が3棟あり大人数が宿泊できそう。湖畔を時計回りで歩き青苔荘に到着。この山荘は小さいながらも風呂が2つあり汗を流すことができる。夕飯は山菜の天ぷらとイワナの塩焼き、キノコ汁などだった。
14日早朝は雨が降っていたものの出発時は曇り。9時頃以降は雨予報だったため、白駒池を眺めたのち麦草峠に引き返す。下山途中に東山魁夷の作品のモチーフとなった幻想的な御射鹿池(みしゃかいけ)に立ち寄ったのち帰宅した。(神谷敏裕)
山行記録に戻る
30.多摩丘陵/生田緑地~とんもり谷戸~妙楽寺
期 日:6月14日(土) 日帰り
参加者:L佐藤邦弘、SL大貫文正、森田隆仁、黒澤寿子、若松節子、中村公子、岩井初江、白石克人、山口音子、野老真子 計10名
コース:向ヶ丘遊園駅9:25―廣福寺9:35―生田緑地ホタル里入口9:50―ホタルの里―戸隠不動尊跡地10:08―尾根―桝形山(展望台)10:15~30―長い階段―奥の池10:45―おし沼広場―とんもり谷戸―水生植物観賞池―東屋11:10~30―初山親水広場11:40―平瀬川―東泉寺12:03―等覚院12:15―妙楽寺12:35~50―五所塚第1公園―五所塚バス停13:00
6月10日に関東甲信地方の梅雨入りが発表され、前日の天気予報は概ね14時ごろから傘マークがつく。集合時刻を30分繰り上げて実施することに。こんな空模様のときは、いつもながら、なんとか雨がもってくれないものかとおもいながらの出発だ。
最初の立ち寄り場所は坂道を少し上がって歴史のある廣福寺。通勤・通学で急ぐ人通りを歩いてきたが、ちょっとお寺の森に入れば、一転して静かな別世界。急な石段を降り立ってすぐに、北野天神社だが、鳥居と急な石段をみて先を急ぐ。特に標識のない森の片隅から山道を降ると、広々とした谷戸が広がり、敷設された木道を歩く。まさに緑がいっぱいの自然空間。ホタルの里と呼ばれ、夜はゲンジボタルが舞うようだ。ホタルの里を抜け出すと、背の高い丸い石柱が何本か立ち、いささか異様な雰囲気。ここは戸隠不動尊跡地。この付近、モミジの木が目立ち、秋の紅葉の季節に訪ねるのもよいかも。上に続く尾根道は桝形山の山頂へと出た。
山城があったという桝形山の展望台はヤグラをイメージしたもので、エレベーター付きと、サービス満点だ。360度の眺望。ちょうどボランティアの男性のガイドさんがいて、ご親切に指をさして、あれはどこと説明してもらう。澄んだ冬の季節は絶景の眺めだろう。しばらくここで展望を楽しんだ。
初山方面に向かって坂道を上がる。上がりきると道路を隔てて、小高い場所がある。おし沼広場といい、おし沼という名は、昔、オシドリが棲んでいた沼があったからだとか。ここから、とんもり谷戸方面へ。山の斜面の階段道を降る途中で恐れていた雨が落ちてくる。傘の準備を急ぐが、雨は直ぐに止む。水生植物観賞池を過ぎたところに東屋・トイレがあり、短い昼食休憩。高台の本遠寺(ほんのんじ)に眠る越路吹雪のお墓は先を急ぐため取りやめ。せせらぎが流れるとんもり谷戸を離れて、平瀬川沿いを歩き、東泉寺~等覚院へ。等覚院の荘厳な山門と手入れがされたつつじ群が広がる境内は印象的。つつじの花が咲くころが待ち遠しいというもの。
今回のメインとなる妙楽寺のアジサイはドンピシャの見頃。山の斜面に咲き競い、白や紫や青などの色とりどりなことはもちろんだが、その色彩はなんとも鮮烈で美しい。拝観料無料というのもよい。驚きと満足のアジサイだった。
帰路のバス停は予定の経路をはずして、一つ手前の五所塚バス停にでてしまったが、幸運にもバスは直ぐに到着。アジサイの花といい、危うい雨ももってくれて超ラッキーな一日となった。(佐藤邦弘)
山行記録に戻る
31.尾瀬/尾瀬ケ原・尾瀬沼
期 日:6月15日(日)~16日(月)一泊二日 曇り/晴れ
参加者:L中村博雄、松宮俊彦、岩月宜雄、延澤英明、宮崎浩之、計5名
コース:鳩待峠11:30-山ノ鼻13:15-竜宮小屋14:45-原の小屋(見晴)15:15泊 7:00発-沼尻8:35-長英新道分岐9:35-大江湿原10:20-尾瀬沼ビジターセンター11:00-三平峠12:35―一ノ瀬13:15
新宿バスタより高速バス「尾瀬号」で快適に尾瀬戸倉に到着、尾瀬戸倉より乗合バスで鳩待峠に着きました。
鳩待峠より登山道の最初は朝までの雨で川と化していました。足元に注意し歩いていたら、ムラサキヤシオの鮮やかな赤色が迎えてくれました。木道は思ったより新しく整備されていて、歩きやすく山ノ鼻まで無事到着出来ました。山の鼻はハイカーがたくさん休憩されていました。山ノ鼻で昼食を済ませ尾瀬ケ原に向けて出発しました。尾瀬ケ原は水芭蕉の時期はすぎていましたが少し残っていて、水芭蕉の白色とリュウキンカの黄色とタテヤマリンドウの水色との色の絨毯を奏でてくれて、ワクワクするトレッキングになりました。見晴では原の小屋に宿泊しました。こぢんまりとした清潔でお風呂も広く大変くつろげました。食事も夜は釜めしを主体とした料理、朝はイワナの燻製もでて良い食事でした。
二日目は最初のころはゆっくりとした登りで、ブナの新緑の中、気持ちよく歩きました。ブナ林を過ぎる所では、水芭蕉が最盛期の群生に出合、はしゃぎました。
その後はタテヤマリンドウ、ショウジョウバカマ等の花の草原の木道を楽しく歩きました。沼尻で休憩し、その後は林の中を通りました。その中ではクロサンショウウオの卵に出合ました。林を抜けると有名な三本松カラマツの大江湿原に出ました。その後尾瀬沼ビジターセンターの休憩所で昼食をとり、近くでは珍しいサンカヨウが咲いていました。その後は三平峠までは登り、その後は下りで一ノ瀬に無事着きました。
一ノ瀬より乗合バスで大清水へ行き、大清水より高速バス「尾瀬号」で帰路につきました。(中村博雄)
山行記録に戻る
32.茨城/筑波山(875.7m)
期 日:6月21日(土) 日帰り 晴れ
参加者:L安瀬はる江、SL山口音子、大貫文正、瀧沢正明、宮崎博之、小林洋子、黒川恵理子 計7名
コース:つくばバスセンター8:55=バス=つつじヶ丘バス停9:40~50―弁慶茶屋跡10:20~30―女体山山頂11:10~20―御幸ヶ原11:40~12:10―男体山山頂12:20~30―御幸ヶ原12:40―男女川湧水地13:05~10―380m13:35~40―筑波山神社13:55―筑波山神社バス停14:08~15=バス=つくばバスセンター14:55~15:1
費 用: あるキップ(北千住より3180円、電車、バス往復代)
手頃な日帰り範囲で遠征気分が味わえる。日本百名山中の最低山登頂。関東平野の大展望。固有種の花の開花、等を期待して計画する。
当日は梅雨時に晴れ予報だったが、急激な気温の上昇で熱中症対策を呼び掛けた。登りのおたつ石コース、下りの御幸ヶ原コースは概ね樹林帯で涼しく、爽やかな汗だった。
筑波山シャトルバスは往復共超満員。座席の確保はできなかった。つつじヶ丘バス停に着くと登山口から急な階段が目に入る。ゆっくり行くが、脚が揃いコースタイムより早かった。稜線からは弁慶の七戻りを始め奇岩怪石を眺めながら女体山山頂に。手狭な岩場の山頂はここも満員。御本殿にお参りして、大展望で解放感を得る。うかつにもガマ石を見落として広い御幸ヶ原に到着。日陰はないが、薄陽で人混みがないので昼食を摂る。
筑波山は双耳峰で、もう一つの男体山山頂に向け、岩混じりの登りを10分程熟す。こちらも本殿があり、その裏側には広大な関東平野が広がっていた。固有種のホザキユキノシタが咲いていたが、地味な花で目を向ける人はいなかった。
杉やブナの巨木が続く下山道は階段や岩混じりで気を抜けなかった。筑波山神社でお礼参りをして、山行を締めくくった。
山行中の花々、シモツケソヴ、ヤマブキショウマ、オオナルコユリ、オカトラノオ、ツルアリドウシ、ホシザキユキノシタ、クモキリソウ、イワガラミ、シオン、コアジサイ、テリハノイバラ、ニイワトコの実等(安瀬はる江)
 おたつ石コース 登山口 |
 弁慶の七戻り |
 オオナルコユリ |
 クモキリソウ |
 シモツケソウ |
 御幸ヶ原 |
 ホシザキユキノシタ |
 男体山山頂 |
 ツルアリドウシ |
 御幸ヶ原コース 下山道 |
山行記録に戻る
33.多摩丘陵/穴川のホタルと讃岐うどんを楽しむ
期 日:6月24日(火) 日帰り 曇
参加者:L佐藤邦弘、SL:大貫文正、安瀬はる江、水内好江、黒澤寿子、峰尾欽二、若松節子
金子盛次、要 加月、山口音子、中村和江、繁村純夫、平本由美子、上野 進 計14名
コース:JR八王子みなみ野駅14:10―みなみ野の丘公園14:20―菖蒲谷戸公園14:45―君田の尾根緑地14:40―宇津貫公園14:45~15:08―宇津貫緑地15:25―七国の尾根展望地16:00―七国峠16:25―大日堂16:30~40―古道―馬頭観世音―うどん屋 K(夕食)17:00~18:30―相原十字路バス停18:38=円林寺前バス停18:45―境川―広田小学校―城山自然ふれあい水路・バンジ谷戸(ホタル観賞19:15~20:00―下馬梅―円林寺前バス停20:29
気温が最も高い午後2時に八王子みなみ野駅に集合。前半は駅から八王子の公園・緑地をつないで歩き、八王子市・町田市の境界尾根を越え、町田市のうどん店で夕食を楽しみ、後半は境川を越え、相模原市となる穴川のバンジ谷戸で飛び交うホタルを観賞しようというもの。
八王子みなみ野駅は約30年前の1997年4月に開通したという。丘陵地に計画的につくられた新しい街だ。10分弱でみなみ野の丘公園入口。坂道を辿ればてっぺんの広場に飛び出す。開けた展望地で山なみが近くにせまる。どうやら奥多摩方面のようだ。空はどんよりの曇り空で蒸し暑い。にわか雨や夜間の小雨も予想され、気になるところだ。
宇津貫公園は広々とした芝生の広場があり、ドクターヘリの離着陸場の看板。昔、五平山といい、山林を残して設計された公園だ。野鳥に詳しい繁村さんの話では猛禽類のツミ(鷹の仲間)が観察できるらしい。山の雑木林の中には急な階段が続き、気合を入れて頂上部に。そしていくつも置かれた石のベンチで一休み。横浜線沿いから宇津貫緑地へ。ここは緑が深く、特別に保全された自然ゾーン。大きな遊水池がひっそりとして水を湛える。さらに奥の森に足を踏み入れたいところだが、保全のため門扉に立入禁止の表示。
八王子・町田市境界尾根を目指して会社の高いビルが並ぶ脇の舗装道路を歩き、境界尾根入口すぐの階段の山道を上がると好展望地。木が伐採され、奥多摩方面の山々や街なみが一望できて、一休みには恰好の場。緩やかに延びる尾根道を行く。蒸し暑いが、軽いハイキング気分を味わいながら七国峠~大日堂に到着。
降って古道を抜け、ほどなくして「うどん屋 K」に。広い店内。各自がお好みの讃岐うどんを注文。デッカイどんぶりのなかにボリュームたっぷりのうどんがワゴンで運ばれてくる。コシの強いうどんと味は概ね好評だったようだ。90分滞在した後、最後の目的となるホタルを見に路線バスで移動。
細い流れの境川を飛び越えて進めば、いよいよ境川水系の穴川だ。ライトをさげて、上流に向って歩き出す。日没時刻の19時ごろだがまだ薄明るい。田園風景が広がる穴川沿いの小径はアジサイロード。が、なぜか花付きが悪い。「城山自然ふれあい水路入口」の看板地点で左折し、鬱蒼とした山裾に進入。バンジ谷戸が現れた。池を通り越し、さらに奥の少し高い場所に東屋とベンチ。
半信半疑で10分程度待ったか。闇夜がせまった19時30分ごろ、忽然とほのかに光る飛翔体。次第にその数は増え、東屋周辺は光を放つホタルが飛び交い、歓声しきりのホタルの乱舞ショーとなった。種類はゲンジボタルのよう。曇天で風もなく蒸し暑い谷戸。ホタルの活動に適した気象条件らしい。いつしか見物人が増え、美しいホタルの乱舞も一段落したところで谷戸を離れ、ライトを照らしながら帰りを急ぐ。それにしても童心を呼び覚ますような夏の夜の感動的体験だった。(佐藤邦弘)
山行記録に戻る
34.岩手県/女神山、駒ヶ岳、牛形山
期 日:6月27日(金)〜29日(日)二泊三日
参加者:L萩原克己、SL大貫文正、北原好、黒澤寿子、飯嶋光江(28日〜29日) 計5名
コース:東京駅7:16=北上駅9:43=女神山登山口13:43-県コ-ス分岐点14:50-女神山15:00~23-登山口16:45=湯川温泉17:40(泊)=夏油温泉登山口11:00-4合目12:10-17合目13:22-駒ヶ岳14:30~15:00-夏油温16:43(泊)~8:00―8合目10:12-夏油温泉登山口11:55=北上駅13:42解散
費 用: 湯川温泉・四季の彩 ¥79,400(4人)、夏油温泉¥80,398(5人)、レンタカ−代金¥25,530+燃料代金¥2,082=¥27,61
27日(金)曇りのち雨
北上駅で3日間レンタカ−を借りました。
錦秋湖・道の駅で食事をして一路女神山登山口(白糸の滝)に向かいました。道の駅の前から小雨模様で、登山口には私達以外誰もいなくて、白糸の滝に下る道を眼下に見ながら道を間違えて姫滝を奥まで行って時間をロスしましたが女神山の登りはブナの原生林の傾斜のき、その後は緩やかな登りが延々と続き県境コ一スとの分岐点に着いて頂上は直ぐと思いきや10分ほどの登りがありました。紅葉の時はブナ林の晴らしい紅葉が観られるでしょう。温泉は温まってなかなか冷めないいい湯でした。
28日(土)晴
北上駅で飯嶋さんを拾い、夏油温泉に向かいました。
今日のコ一スは標高差はあまりないのですが距離があり、ダラダラの登りで頂上までの登りで会ったのは中年の夫婦と、頂上にいた前日7合目でテント泊した地元の山岳会?の人が狩り払いをしてくれた奇特な有り難い人の2組でした。頂上からの展望は360度の素晴らしかったです。
下山してうち風呂しか入りませんでしたが、夏油温泉も今回で4回目ですが昔に比べれば(観光ホテル、国民宿舎等4件くらいありました)寂れましたね!
29日(日)晴
飯嶋さんと別れて四人で牛形山に向かいました。
2年前に焼石連峰縦走して来た分岐点を後にして、単独行者が足早に追い抜いていきました。5合目までは比較的緩やかな登りで、その後は尾根の北側をトラバ一スする道になり通過するときには気をつけました。
7合目の沢の先の通過が難しいので3人にはそこで待ってもらいましたが、その先尾根を回り込んだが後が急ながれ場になっていてあまり掴む枝もなく何回かズルズル滑ったのでその先に行くのは止めました。8合目の手前でした、若い単独行があっというまに追い抜いていきましたが!歳をとりバラン感覚が悪くなったのを痛切に感じました。
ケガでもして皆さんに迷惑を掛けるわけにいかないし60年間山行で一度もケガをしたことないし!又の機会にと思いました。
来年の春山でもう山を引退するかな!(萩原克己)
山行記録に戻る
35.富士山/五合目
期 日:6月28日(土) 日帰り 晴れ
参加者:L神谷敏裕、SL伊藤有子、横川芳江、要 加月、山口音子、岩井初江、支部外1名 計7名
コース:富士山駅9:30=馬返9:55~10:05-二合目10:53~10:56-三合目11:15~11:22-四合目11:45~11:50-井上小屋跡12:00~12:05-五合目(佐藤小屋)12:55~13:20-泉ヶ滝13:38-富士スバルライン五合目13:45~14:10-御庭入口15:20~15:54=河口湖駅17:35
富士山駅に集合し馬返までワゴン車で入る。タクシー会社が運営している路線。予約不要で\500で乗車できるので便利。この日は4台分の乗車があった。ワゴン車は冨士浅間神社の脇を入って馬返に向かう。神社辺りから、7月に開催される富士登山競争の練習をするトレランランナーが行き交う。
馬返で下車するとひんやりして心地よい。準備して出発。ランナーが通るときは一旦立ち止まったりするが、比較的登山道が広いので渋滞することはない。数回休憩して佐藤小屋に到着。ここも多くのランナーが休憩している。我々も昼食を摂り、今度は富士スバルライン五合目に向かう。同じ五合目だが、なだらかに坂を上っていく。今度は観光客が多くなる。観光客相手の乗馬も行き交う。
富士スバルライン五合目で少し休憩したのち御庭に向かう。シャクナゲが多いが開花には少し早い。蕾は所々といった感じ。代わりにイチヤクソウが満開だった。1時間強歩いて御庭入口のバス停に到着。トイレ裏の小高い丘に上がると絶景の富士山が見えるとのことなので上がってみる。観光スポットではないが、間近に赤い富士山が見えてすばらしい。
当初は奥庭荘に宿泊予定で翌日、青木ヶ原樹海に向かって下山を計画していたが、今年は宿はやっていないとのこと。今回は麓に下りるバスに乗車し、日帰りで帰宅した。梅雨は明けていないが、天気に恵まれた清々しい山行だった。 (神谷敏裕)
山行記録に戻る
36.箱根/芦之湯~箱根の森~元箱根
期 日:7月8日(火) 日帰り 晴
参加者:L佐藤邦弘、SL大貫文正、伊藤和良、黒澤寿子、岩井初子、森田隆仁、宮崎博之、瀧沢正明、助廣弘子、北原 好、上野 進、支部外:木庭寿子、高木千代美 計13名
コース:小田原駅8:35=東芦の湯バス停9:28―芦之湯―東光庵熊野権現旧跡9:32~42―曽我兄弟の墓―精進池10:23―六道地蔵10:30―箱根の森・休憩地11:25~12:00(昼食)―お玉ヶ池12:11―展望広場12:22―箱根旧街道石畳12:20―権現坂―興福院―元箱根バス停12:55
下界は気温35℃が予想される猛暑日だ。このコースの最高点は900m弱、最低点700m強程度、石仏群巡りと呼ばれる緩やかコースという予備知識。バスは渋滞することもなく、順調に高度上げて東芦の湯バス停に。ここは標高約850m。やはり下界に比べれば涼しい空気が流れる。150m程度西に歩くと、広い敷地に大きな旅館が現れた。山に囲まれ平たい地。閑静な温泉地といったところか。廃屋と思われる施設も。石段を上がりきると茅葺屋根の東光庵がひっそりとあった。なかなかの風情。江戸時代には湯治で訪れた文人が集ったという。賀茂真淵や本居宣長も。創業1715年だという旅館の前には大きな釜から温泉水が溢れかえり、硫黄のニオイが立っていた。
国道沿いの遊歩道へ。雑木林のなかは風通しが悪く、蒸し暑さを感じる。緩やかな上りの道が続く。最初は曽我兄弟の墓と虎御前の墓。巨大な五つの石が積み上げられ、圧倒せずにはおかない。ヒンヤリとした国道の下の地下道をくぐると岩壁に幾つもの磨崖仏(二十五菩薩)が現れ、目をみはる。さらに進んで再び地下道をくぐり抜ける。うす暗い覆屋の中を覗くと巨大な六道地蔵(磨崖仏)。永い年月、険しい箱根の山を越える旅人をじっと見守ってきた石仏群。信仰と歴史の重さが否応なく伝わってくるというものだ。
背後に駒ヶ岳を控えた精進池。絶景のロケーションだ。みんなで写真におさまる。山道は思わぬ長い下り坂が続く。高度100m程度降ったか。降り立った分岐で箱根の森に向かい、東屋のある休憩広場で昼食。ここから降りの道を進むと、ほどなくしてお玉ヶ池。ここもまた絶景だった。穏やかな水面が広がり、向こう側に上二子山、下二子山のどっしりとした姿。立ち止まって、一斉にカメラが向けられた。お玉ヶ池から南に山道を登り返し、名称を疑う展望広場を経て箱根旧街道へ合流。苦難の末に整備された石畳の道は、決して歩きやすい道ではなかったが、雨や雪の際の状態を考えれば腑に落ちる。
歴史を感じる芦之湯や東光庵、そして石仏石塔、静かな池と取り囲む山々の風景。花を咲かせた山野草は端境期で少なかったようだが、猛暑を逃れて箱根の魅力を楽しむことができた。そして眺望を満足さてくれた山のお天気に感謝!いくらかショートカットして帰路のバス停は元箱根。ここで無事に終了、解散とした。(佐藤邦弘)
山行記録に戻る
37.富士/富士スバルライン五合目~三合目
期 日:7月21日(月、祝) 日帰り 晴れ一時曇り
参加者:L安瀬はる江、SL佐藤邦弘、SL繁村美知子、助廣弘子、竹田早苗、鎌田文子、武末範子、大貫文正、白石克人、北原 好、英賀昇子、中村博雄、清水佐基子、鬼束しづ子、曽我幸子、宮崎博之、中村公子、黒川恵理子、高原春子(支部外)
計19名
コース:八王子駅7:00=バス=奥庭駐車場9:00~10=五合目9:15~30―お中道休憩10:40~55―奥庭駐車場11:45~55―奥庭展望台12:15~45―三合目14:35―樹海台駐車場15:00~20=バス=八王子駅18:20
費 用: バス代 4100円/一人
去年と同じコースを日程を変えて計画。お中道の林下はどこも一面シャクナッゲの木で埋まる。去年は裏年で花付きが悪かった。シャクナゲを期待する声や山域に興味を持つ声を受けてバスを手配した。皆様の絶大なご協力を得てバスでの山行に漕ぎつけた。直前のキャンセルや予定したバス車体の不具合等で変更が相次ぎ奔走した。SLの協力も得て、切り抜けた。
当日は雲が多めで山頂や山麓は垣間見る程度だった。都合よく降雨はなかった。雲間の空は紺青で、ほど近く、砂礫の茶色や草木の緑と引き合っていた。お中道はシャクナゲロードになっていた。蕾もあり、見頃だった。足元には独得な草花が咲き誇っていた。ここでは富士山の雄大さを実感できた。小学生の集団にも出会い、人が多かった。続くお庭、奥庭と景観が変わる。今年も奥庭展望台で昼食。よく見ると木の枝下には稀少なランが群れていた。撮影会になった。ここで体調を考慮されて二名がバスに戻った。さらに、三合目からは原生林へと一変する。期待したコイチヤクソウを発見。山行を通してイチヤクソウ属の数種にで合え、大収穫だった。去年との10日間の日程差が花を介して判った。
花への関心度に個人差があり、しばし足並みに影響したが、双方で譲り合い、調整できた。
山行中の花々、ミヤマオトコヨモギ、アズマシャクナゲ、ハナヒリノキ、ベニバナイチヤクソウ、マルバノイチヤクソウ、コバノイチヤクソウ、ジンヨウイチヤクソウ、イチヤクソウ、コイチヤクソウ、フジハタザオ、コケモモ、オンタデ、メイゲツソウ、イワオウギ、ミヤマハナゴケ、ヤナギラン、ハソショウヅル、ミヤマフタバラン、コフタバラン、ホタルブクロ、キソチドリ、シャクジョウソウ、コイチヨウラン、ツメゴケ、ヒカゲノカズラ、ギンリョウソウ、ミヤマウズラ、シモツケソウ、ヒカゲノカズラ等(安瀬はる江)
山行記録に戻る
38.八ヶ岳/美し森~天女山
期 日:7月26日(土) 日帰り 曇時々晴
参加者:L佐藤邦弘、SL大貫文正、安瀬はる江、黒澤寿子、中村公子、黒川恵理子、繁村純夫、繁村美知子、助廣弘子、杉江秀明、中村博雄、堤 理恵子 計12名
コース:JR清里駅11:00=美し森バス停11:10―美し森頂上11:25―たかね荘(閉鎖)11:38―羽衣池11:50―川俣川渓谷12:30~12:50(昼食)―八ヶ岳牧場13:05―展望台13:30―天女山14:25―天女山登山道口―天女山入口ゲート14:57=タクシー=JR甲斐大泉駅15:10
清里駅前バス停から清里ピクニックバスは遅れてくる乗客を待って、10分程度遅い発車。夏休みの観光旅行か、家族連れも目立つ。美し森バス停で下車。天女山への登山口はすぐのところに。立派な木の階段が敷設され、上に向って延びている。陽射しは焼けるように強く、スタートから思わぬ強力なパンチをもらったようなものだ。木陰がなく、汗が噴き出て流れ落ちるなか、必死に耐えて階段を登り切り、美し森山頂に着く。樹林の中の山道になってきたが、歩幅の合わない木の階段道も出てきて、緩やかだが、快適とはいかない。標高1610mの羽衣池が現れたときはホットする。が、池は草が伸びて、水は枯れ、荒れたような風景にいささか戸惑う。
カラマツとクマザサの深い緑色に輝く森のなかの道を降る。その森は何度も振り向いて、その美しさを確認したくなるような世界だった。沢音が耳に届いてきた。昼食を予定していた川俣川東沢。水の流れはたいしたことはなく、小さな飛び石が並べられた箇所を難なく渡る。すでに数人の登山客が川辺でお昼を食べていた。我々も石のある川辺に腰をおろす。雷鳴が聞こえ出し、昼食後は雨具を付けて出発。まもなくして、広々と開けた山麓の大草原と牧草地に飛び出す。牛がのんびりと草を食む。なんとも寛げるいい光景だ。さらに進んで明るく開けた土の場所にベンチとテーブル。展望台だ。その付近から見る天に向って鋭く突きあげた赤岳の威容は神々しい。さすがに八ヶ岳連峰主峰の趣を放っている。
天女山山頂への道は直登の道を選択。まさに最後の踏ん張りどころ。一歩一歩重たい足を交互に引き上げる。山頂には東屋と大きな石碑に山頂を示す文字が刻まれていた。最後の休みをとり、天女山入口ゲートにタクシーを配車した時間を考えに入れ、下山開始。尾根筋の降りは予想をはるかに超える速さで一気に。6人乗りタクシーはまだ来ていなかったが、ほどなくして到着。ピストン輸送で12人は無事に甲斐大泉駅へ。
変化のあるハイキングコースいう触れ込みに期待しての計画。八ヶ岳山麓の森と展望と草原と牧場と沢など、結果は猛暑のなか遠くまで来た甲斐があったというべきか。恐れていた雷雨に見舞われることもなく、計画通りに歩けたことを喜びたい。意外にも他に歩いている人とあまり会わない、静かなコースであったことも付記しておいてよいだろう。(佐藤邦弘)
羽衣の池 |
緑まぶしい美し森 |
カラ松と熊笹の道 |
川俣川東沢で昼食 |
牧場の道 |
のどかな 八ヶ岳牧場 |
展望台にて |
展望台付近からの赤岳 |
沢を渡る |
天女山山頂 |
山行記録に戻る
39.東北/鳥海山
期 日:7月28日(月)~29日(水) 夜行一泊二日
参加者:L松宮俊彦、SL伊藤有子、油田まり子、岩井初江、水内好江、要加月、瀧沢正明 計7名
コース:28日(月):酒田駅6:30=鉾立登山口7:30~45―御浜小屋10:00~15―七五三掛11:15―千蛇谷見晴らしベンチ11:40~12:10―大物忌神社(御室)14:15~15:10―新山山頂15:55~16:05―御室16:30(泊)
29日(火):御室6:15―外輪山大清水分岐6:35~40―伏拝岳7:30~35―上部の雪渓8:30―下部の雪渓9:20―河原宿小屋跡10:10~30―滝ノ小屋11:50(解散)/~13:00―滝ノ小屋駐車場13:30~40タクシー=酒田駅/~12:10-(湯の台道)―二本杉13:45―蓬莱山14:20―鳥海山荘15:50
費 用:ジャンボタクシー20960/台、御室小屋11000/人+8800(個室) 各自交通費
7月28日午前6時半酒田駅前に7人が集合。結局夜行バ利用は一人のみで、他の人は前泊だった。荷物はシュラフが入っているため全員大きい。ジャンボタクシーで鉾立登山口駐車場に7時半頃到着した。広い駐車場の3分の1程度、それでも約100台は駐車しており人気の高さがうかがえた。準備を整え出発、登山道は30~50cm四方の石畳が続いており歩きやすい。1時間ほどでニッコウキスゲの群落に出合ったので一息入れた。天気は薄曇りから晴れに変わり暑い。10時頃に御浜小屋に到着。鳥海湖の周りには雪が残っており、斜面には鳥海アザミやハクサンフウロ、ハクサンシャジン、トウゲブキ、クルマユリなどが咲き乱れていた。扇子森から御田カ原までは緩い登りと下りなので両側のお花畑をゆっくりながめる余裕があった。七五三掛(シメカケ)と外輪山との分岐を過ぎ千蛇谷の雪渓が見下ろせるベンチで昼食とした。
眼下には細長い雪渓が横たわり、正面にはこれから登る山頂までの急な緑色の斜面とその上の岩稜帯がそびえていた。雪渓の幅は30m程でアイゼンをつけずに楽しみながら渡れた。そこからは急な登りで足元の岩も不規則な大きさで歩きにくい。荷物の重さもじわじわと効いてきて、なかなかペースが上がらない。足をつる人も出てきた。何度か休みながら、多少前後に差ができたが、なんとか2時半頃には全員御室小屋に到着した。部屋は個室で、30分程休んでから新山山頂を目指した。新山は大きな岩の重なりでできており方向を見失いやすいが要所には白い矢印がついているし、岩も乾いている。登りながら日本海や歩いて来た登山道も見下ろせて高度感はあるが怖くは無かった。頂上は狭かった。下りは胎内くぐりを通り、周回する形で小屋に戻った。小屋の奥に大物忌神社があり、石垣の間には鳥海フスマだろうか小さな花が咲いていた。水が乏しいため無料の水の提供は無く、トイレの手洗いも天水のみ利用可だった。日本海に沈む夕日を眺めてから、すぐに眠りについた。
29日4時半頃の日の出の直後、西の日本海方面の空と海をスクリーンにして影鳥海を見ることができた。思ったよりずっと大きくはっきりしており本当に山があるようだった。それが15分くらいだろうか続いた。出発は6時15分、まず外輪山の尾根迄の急な登りを約20分。登りきると360度の展望。北側には新山がでんとそびえその下に御室小屋、西にはこれから歩く外輪山の岩壁やその先に日本海、南には月山とその周辺の山々、また東には朝もやたなびく中に重畳たる山々の連なりがあり、それらが早朝の強い陽の光の中にくっきり映えていた。
外輪山を伏拝(フシオガミ)岳まで歩き新山方面の景とに分かれ、下りの湯の台道に入った。しばらく草付きの急な道をどんどん下っていく。斜面にはイワギキョウ、ハクサンシャジン、各種の黄色い花々が咲いている。一つ目の雪渓の手前で軽アイゼンをつけて横断した。その先の下り道にはミヤマキンバイ等の黄色い花や、岩鏡、ハクサンチドリ、それにチングルマの群落も出てきた。二つ目の雪渓は大きく長い。横の登山道を歩けば河原小屋跡の付近まで行けそうだったが、歩きにくい道だしせっかくアイゼンを持ってきたので途中から雪渓に入った。雪渓は思いの外歩きやすく、傾斜もそれほどきつくなかったのでどんどん下って行った。結局雪渓の末端まで約30分歩くことができた。そこから河原小屋跡までは近かった。小屋跡からの道は、ズシリと重いリュックに加え、歩きにくい急な下りなのでゆっくりペースにならざるを得なかった。少し平らになると雪渓からの雪解け水の小さな流れが続いていた、そこを踏み石伝いに渡っていくと滝ノ沢小屋に着いたが、暑さも加わり疲労困憊の感があった、幸い滝ノ小屋は板敷きで風もよく通るので上がってゆっくり休むことができた。
後は下りを20分程で駐車場に着く。ここから本隊と別動隊に分かれるので、支部山行としてはここで解散とした。本隊6名はゆっくり休んだ後タクシーの待つ駐車場へ。別動隊1名は湯の台道を尾根の末端まで歩くべく南の尾根を進んだ。ここから先の道はあまり歩かれていないうえに灌木と笹薮に覆われているので、熊用心のため熊鈴と笛、更に大声も加えて歩いた。それでも1時間半ほどで灌木は背の高いブナ林と変わり、最後の約1時間半はよく整備されたハイキングコースとなり無事鳥海山荘に到着した。天候に恵まれ、鳥海山らしい雪渓と花々と岩のコントラストを、日本海の見晴らしも加えて、存分に味わうことができた。(松宮俊彦)
山行記録に戻る
40.北ア/雲ノ平
期 日:8月3日(日)~6日(水) 3日:晴れ時々曇り、4日:晴れ、5日:曇り時々小雨
参加者:L神谷敏裕、SL要 加月、山口音子、佐藤由佳(支部外) 計4名
コース:
8/3(日)富山駅6:25=折立7:30~7:45-三角点9:25~9:30-五光岩ベンチ11:00~11:18-太郎平小屋12:05~12:35-第一渡渉点13:20~13:35-薬師沢小屋15:15泊
8/4(月)薬師沢小屋5:45-アラスカ庭園8:10~8:30-祖母岳9:42~10:02-雲ノ平山荘10:25~11:30-祖父岳13:08~13:30-スイス庭園14:30~14:38-雲ノ平山荘15:30泊
8/5(火)雲ノ平山荘5:30-黒部川源流7:45-三俣山荘8:30~9:00-双六小屋11:25~11:55-弓折乗越13:10~13:15-鏡平山荘13:58~14:10-シシウドガ原14:45-秩父沢出合15:30-小池新道登山口16:10-わさび平小屋16:30~16:50-新穂高ロープウェイ駅17:50~18:10=栃尾温泉ジャンダルム18:20
8/6(水)上栃尾8:07=平湯温泉8:28~9:35=中央道日野13:45=バスタ新宿14:15
費 用 薬師沢小屋13,000円(ココヘリ割500円)、雲ノ平山荘16,000円、ジャンダルム8,950円、タクシー(富山駅~折立、有料道路代込み)22,000円、バス(上栃尾~平湯温泉)630円、高速バス(平湯温泉~バスタ新宿)7,500円
初日はタクシーをチャーターし折立へ。太郎坂を太郎平に向けてひたすら登る。日曜日だからか下山者が多い。太郎平で休憩。少し雨に降られたがすぐに止み、今度は薬師沢に向かって下る。とにかく暑いが沢付近になると涼しい。沢を何度も越えて薬師沢小屋に到着。夕方外で涼んでいると突然の雷雨。着後でよかった。
二日目は朝からよい天気。小屋前の橋を渡り沢から急登を登る。昨晩の雨で濡れていて滑りやすい。急登が終わり暫く歩くとアラスカ庭園。周辺の山々はほとんど雲に覆われているが、お花畑を眺めながら歩を進めるとどんどん雲がとれ、やがて薬師岳、赤牛岳、水晶岳、ワリモ岳、黒部五郎岳などの全貌が見えてくる。祖母岳(ばあ)の頂上からは雲ノ平の彼方に水晶岳が聳える。一旦、雲ノ平山荘で昼食、荷物を一部デポし、祖父岳(じい)に向かう。頂上からは今まで見えなかった鷲羽岳が現れる。水晶岳は手に届くよう。祖父岳から下山し雲平山荘に引き返す。途中スイス庭園に立ち寄ると、薬師岳と赤牛岳に挟まれた雄大な高天原が広がる。テント場で飲み水を汲み雲ノ平山荘に戻った。
三日目は一転、朝からガスが立ち込める。昨日歩いた祖父岳への道を歩き、日本庭園を下りていくと右側に巨大な雪渓が見えてくる。黒部川源流はロープを伝って渡り、今度は三俣山荘に向けて登り返し。この辺りでは断続的に小雨に合う。三俣山荘の二階で暫し休憩。天候が良くないため、計画していた三俣蓮華岳、双六岳は諦めて巻道を行く。双六小屋には昼前に到着。明日からは悪天候の予報で、本日午後はまずまずの天気。メンバーの余力もあることから双六小屋はキャンセルし、新穂高温泉への下山を決断。弓折乗越からはひたすら下降。鏡平山荘で小休止。わさび平小屋で電波が通じたので宿を手配。満室や休館で数件断られたものの、栃尾温泉の穂高岳山荘直営のジャンダルムという宿が、休館にも関わらず受け入れてくれた。温泉もあり綺麗な宿。急な予約にもかかわらず、すき焼きまで出して頂き、疲れた体を癒すことができた。最終日は、麓も朝から小雨模様。朝のバス便に変更し平湯温泉経由で帰宅した。
悪天候予報のため三日目は長距離の歩行となりましたが、めげずに歩き切ったメンバーに感謝いたします。(神谷敏裕)
 タテヤマリンドウが満開 |
 薬師沢小屋前で くつろぐ |
 薬師沢の吊り橋を渡る |
 奥日本庭園にて |
 雲ノ平の後ろに 水晶岳 |
 祖父岳山頂にて |
 黒部五郎岳の カール |
 雲ノ平の先に 薬師岳 |
 スイス庭園から |
 雷鳥に出会う |
山行記録に戻る
41.高尾/小下沢ウォーターウォーキング
期 日:8月16日(土)日帰り 曇り
参加者:L矢澤孝二、髙木弘司、小磯登志子、水内好江、助廣弘子、松宮俊彦 計6名
コース:高尾駅8:32=大下8:47~50-梅の里上(入渓)9:00~20-高尾の森ベース11:35~12:55-梅の里入口13:35~41=高尾駅13:55
猛暑続きの中、涼を求めて裏高尾の小下沢へウォーターハイキング。
小下沢林道のフェンスが切れた処から入渓。今日は何組か入っているようだ。水量は多くはないが、適度な冷たさが気持ち良い。蝉時雨の下、小さな滝(数十センチ)や滑をじゃぶじゃぶ歩いて行く。深いところでも股くらい。澄んだ流れや涼やかな風は、爽やかな暑さをもたらしてくれた。
高尾の森ベースの、景信山登山口の木橋で遡行は終了。あとはゆっくりと昼食、流れを右に見ながら林道を歩いて戻る。
途中で二人の渓流シューズのソールが剥がれるアクシデントがあった。前兆はわからないようだが、特に久しぶりに掃く時には注意したいものだ。(矢澤孝二)
山行記録に戻る
42.富士/青木ヶ原樹海(花山行)
期 日:8月31日(日) 日帰り 晴れ一時曇り
参加者:L安瀬はる江、SL佐藤邦弘、SL中村博雄、森田隆仁、助廣弘子、上野 進、竹田早苗、黒澤壽子、佐藤邦弘、杉江秀明、山口音子、大貫文正、松本悦榮、繁村美知子、白石克人、瀧沢正明、岩井初江、水内好江、要 加月、中村公子、井口良子(支部外)高原春子、江角真由美 計23名
コース:八王子駅7:30=貸切バス=精進湖民宿村9:15~20-休憩10:20~30-富岳風穴駐車場12:00~10-風穴入口12:15~40-富岳氷穴13:05-富士八景13:40~45-竜宮洞穴14:05~15-根場入口駐車場15:00~15=貸切バス=八王子駅南口18:50 バス代 3600円/一人
当初の計画は公共交通機関でのアクセスだった。参加者の状況で貸切バス利用に変更した。予報が出ていた降雨もなく、暑い一日だった。酷暑の時期に富士山の裾野は冷涼でコースも多い。珍しい植物があり、興味深い場所だ。今回は樹海の西から北へのコースをとった。遊歩道が整備され、随所に道標もある。林は針葉樹が主で、広葉樹も混在している。溶岩流の林床は大小の洞穴がある。、アセビやミヤマシキミの低木、種々の苔類が緑に覆っている。最近の雨不足で少々乾燥気味だったが、独得な景観で筋状の木漏れ日は美しさを一層増していた。
目的の花、ミヤマウズラは丁度見頃で彼方此方、かなりの株があった。ひとしきり愛でたり、撮影するとミヤマウズラに足が止まらなくなった。空は仰げず、終始同じ景観で、単調になり、お喋りが弾んだ。
風穴駐車場でトイレを済ませ、遊歩道側入り口に行く。幅広ベンチが3基。先客が2人。背中合わせに譲り合って座り昼食にした。
氷穴で三湖台への登頂希望を図ったが、巻道を全員で龍宮洞窟に行くことにする。分岐にいくとそのルートが不明瞭だった。稜線を登りにして、更に希望者で富士八景まで往復した。樹海の閉塞感から解放され、雲に覆われた北側半分の富士山が望めた。この先竜宮洞窟では天然冷蔵庫に冷やされ、少し元気がでる。また、樹海コースに戻り西湖遊歩道でバスが待つ駐車場に急いだ。
遊歩道では歩行者が稀だったが風穴や氷穴は多かった。出発時は番号で点呼をかけて確認をとった。全員のご協力で安全な距離間で歩け通せ、感謝です。SLの強力なサポートにも感謝です。
山行中の花々、コクラン果実、ヒトツボクロ果実、ミヤマウズラ、ミヤマシキミ果実、ミヤマトウバナ、ヒノキゴケ、ホソバコケシノブ、キッコウハグマ蕾、トウゲシバ、ツルリンドウ蕾、ハエドクソウ、バイカオウレン葉、キンミズヒキ(安瀬はる江)
山行記録に戻る
43.奥多摩/雲取山
期 日:9月7日(日)~8日(月)一泊二日 晴れ一時曇り
参加者:L安瀬はる江、SL高木弘司、中村和江、水内好江、宮崎博之、要 加月、延澤英明(計7名)
コース:奥多摩駅8:35=鴨沢9:06~10―村営登山者駐車場9:40~50―鴨沢登山道入口10:00―小袖10:30~40―堂所11:40~50―七ツ石小屋12:50~13:15―ブナ坂13:50―奥多摩小屋14:35―小雲取山15:15~20―雲取山山頂15:50~16:00―雲取山荘16:20(泊)~5:30―芋のノ木ドッケ6:50~7:00―白岩小屋7:30―前白岩の肩8:20~30―霧藻ヶ峰9:30~40―三峯奥宮鳥居10:55―三峯神社バス停11:10~40=バス=西部秩父駅
宿泊代 1泊2食付き 9500(新ハイ割引) 個室料金 2室 8000
今回の山行はリクエストもあり、気になる花の情報も得ていたので、計画。雲取山も最後のチャンスかなと。
7日 鴨沢で下車した登山者は我々の他に2名だった。集落を抜け、登山道に入ると樹林帯で、陽射しから逃れた。登山道は登り尾根を西から東へと巻いて、七ツ石山へと導いている。雪がついたこの道を歩いた日を回想しながら我慢の時間だった。日曜日で多くの下山者とも行き交う。急斜面の細い巻道で気を遣う。平将門迷走ルートと称され、案内板が随所にある。けれど読む余裕はなかった。写真を撮って、帰宅後確認すると、なかなか興味深かった。ヤマジノホトトギスが沢山咲いて元気をもらった。
先頭のSLにシルバーペースでお願いして、七ツ石小屋に到着でき一安心。豊富な水が引かれ、軽食や飲み物が販売されていた。七ツ石山山頂はカット。巻き道の水場で喉を潤し、ブナ坂へ。広い稜線にでて展望もあり、開放的になる。小雲取山への急登を熟し、乗り越えると稜線の先には避難小屋の赤い屋根がみえた。そして大きな山名石塔が懐かしい山頂へ到着。ガスが広がり展望はなかったが感無量。
山荘へは登りとは違った様相で、急下降。小石も多く、落石に注意した。奥秩父特有の原生林で、苔むして鬱蒼としている。疲れもピークで慎重に下った。この日は25名位の宿泊者で静かだった。夕食まで、外のベンチで談笑。闇になると木立の合間には夜景が広がり、部屋からは満月が望めた。
8日 午後からの雨予報で、5:30に出発。大きな太陽が既に上がっていた。三峯神社への下山路は趣あるコースで変化に富んでいる。勾配はきつく、アップダウンもあり、露岩帯もありで油断できない。けれど脚も揃い、快調な歩だった。途中雲取ヒュッテ、白岩小屋は廃屋で崩壊寸前だった。小屋の裏に回ってみると、大展望で、和名倉山から両神山までが並んでいた。このコース唯一の霧藻ヶ峰の休憩所は真新しい。喫茶の営業もあるようだ。すぐ上にはトイレ棟もあった。
今回の目的の花、シラヒゲソウの株も多く、丁度見頃。シロヨメナは大規模な群生もあり、見応えがあった。前日と全く違う、このようなコースを楽しみながら、順調に下山。予定のバスの1本前に乗車できた。雨もなく酷暑の三峯神社では山に戻りたくなった。
山行中の花々、キズタ、ヤマジノホトトギス、ゲンノショウコ、フイリヒナスミレ葉、イシミカワ、カタバミ、ハキダメギク、メタカラコウ、マルバダケブキ、アキノキリンソウ、ヤマハハコ、ツリガネニンジン、タマガワホトトギス、ホタルブクロ、ウメバチソウ、バイカオウレン葉、シラヤマギク、トリカブト、ダイモンジソウ、レイジンソウ、シラヒゲソウ、ハナイカリ、トウヒレン属、ミヤマモジズリ、ウメガサソウ実、オトギリソウ、ヨツバムグラ、ヤナギラン、クルマユリ(安瀬はる江)
山行記録に戻る
44.奥武蔵/嵐山渓谷・大平山を歩く
期 日:9月13日(土) 日帰り 曇
参加者:L佐藤邦弘、SL大貫文正、本山まり子、岩井初江、井口良子、上野 進、飯嶋光江、森田隆仁、北原好、黒澤寿子、中村博雄、 計11名
コース:武蔵嵐山駅10:01―菅谷館跡10:20―光照寺11:03―春日神社11:30―大平山11:50―東屋・大平山展望地(昼食)11:53~12:25―往路戻る―大平山―北側登山口(遠山道)12:40―嵐山渓谷入口―展望台・嵐山町名発祥之地の碑―与謝野晶子「比企の渓」歌碑13:15―嵐山渓谷突端13:17―往路戻る―展望台・嵐山町名発祥之地の碑―塩沢冠水橋―往路戻る―飛び石13:50―バーベキュー場・売店14:05~40―休養地入口バス停14:51=武蔵嵐山駅15:03
埼玉県の嵐山町という名は京都の嵐山に景観がよく似ていることに由来し、嵐山渓谷は紅葉の人気スポットとして知られている。今回、たくさんの人で賑わう時季を避け、お手頃な嵐山渓谷とその周辺を歩く計画を立ててみた。
集合時刻の直前まで雨が降り続き、雨は止んだものの雲が多く、傘の出番がないことを祈って、武蔵嵐山駅から菅谷館跡に向けて歩き出す。駅前は人通りがなく、閑散としている。幹線道路の向こう側に大きな森。鎌倉時代の武士 畠山重忠が住んでいた館跡とされる。森に囲まれて蒸し暑い。小高い場所に重忠の像が立つ。堀や土塁が残る広々とした菅谷館跡を半周して離れる。車道を横切り、林を抜けると田園風景と民家がチラホラ。そして正面に嵐山町最高峰 大平山179mが姿。
光照寺の裏の山道を通り抜け、春日神社へ。道はほぼ明瞭だがやぶっぽい。蜘蛛の巣が立ちはだかる。おまけに雨後のため、下草や垂れた樹木が濡れている。衣服は濡れるがままに、ストックで蜘蛛の巣を払いのけながら進んで脱出した。天岩戸嵐山明が指宮の立ち寄りはカット。春日神社の社殿の横が大平山の登山口。尾根筋に付けられた擬木の階段。きつい直登だ。汗がしたたり落ちる。今日一番の難所。必死に登りきると山頂。展望はない。山名板が木に取り付けられ、神社があった。南に少し進むと南東が開けた展望地。東屋とベンチがあり、休憩にはもってこい。すでに老夫婦らしき二人が食事中。我々もここで昼食。曇ってはいたが、嵐山町や鳩山町方面を望むことができた。
昼食後、山頂に戻り、北西に向かうルートを降る。目指すは嵐山渓谷。車道を経て、トイレが近くにある嵐山渓谷入口に着く。ここから整備された広い山道が延び、右側の下方には槻川が流れる。道は展望台が建つ所に。その近くに嵐山町名発祥之地の碑。紅葉が美しいに違いないモミジの森の道を進むと、与謝野晶子の歌碑を左側に見る。さらに進んで突端。槻川が流れ、渓谷美を造り出していた。引き返して、バーベキュー場に向かう。ゴールは近い。途中、川岸に降りると、石造りの塩沢冠水橋が架かる。周囲の渓谷美とマッチして、なかなかの風情。さらに川下に行くと飛び石を使って対岸に渡れる箇所があり、楽しませてくれる。水量が多いと渡れないときもあるようだが、問題なし。付近では若い男女のグループが川に入って戯れていた。
広い河原を利用したバーベキュー場に着いたのは14時少し過ぎ。ここから帰りのバス停はすぐ。乗車時刻は14時51分。時間の余裕をどう埋めるか気をもんだが、そこには売店があり、超うれしいことにアルコールも。ベンチに座ってワイワイ談笑し、冷たい一缶を飲み干すと、ちょうどバスの時刻。バスは時刻どおりに来て、気持ちよい気分で帰路に就いた。(佐藤邦弘)
山行記録に戻る
45.あきる野市/天竺山~高尾公園 (本部集中)
期 日:9月15日(月・祝) 日帰り 曇り
参加者: L神谷敏裕、SL大貫文正、SL竹田早苗、佐藤邦弘、宮崎博之、松宮俊彦、黒澤寿子、矢澤孝二、澤田治之、助廣弘子、支部外1名 計11名
コース:武蔵五日市駅9:35-三内神社9:35~9:58-天竺山10:13~10:22-横沢入10:50~11:03-大悲願寺11:10~11:35-高尾公園(本部集中イベント)11:50~14:50-JR武蔵五日市駅15:10
4月の開催が雨で中止となり、残暑厳しい9月の実施となった。
武蔵五日市駅で集合し、まず徒歩で三内神社に向かう。JRの踏切を渡るとすぐに鳥居があり、その先から急な階段となる。ここで支部外の参加者は離脱し直接会場に向かうことに。残りのメンバーは階段をあがり三内神社の境内に入る。更に断続的に階段を登っていくと天竺山の頂。東側が開けており、サマーランドやあきる野市街などが望める。石山の池まで下り、蜘蛛の巣が至る所にあるあまり歩かれていない尾根沿いを行くと、やがて谷戸の横沢入に至る。横沢入にある休憩所で休憩。建物内は涼しく心地が良い。少し歩くと大悲願寺の境内となる。萩で有名なお寺だが、花の開花には少し早かった。素晴らしい彫刻が施された観音堂、仁王門などを観覧し、イベント会場の高尾公園に向かう。
高尾公園はあまり広くはないが、屋根のある舞台がありイベント実施には適地。今回は120名ほどの参加だったのでちょうどいい広さだった。当日の山行報告や各支部の紹介、本部リーダーの紹介、本部役員の紹介などが行われる。その後は全員参加のじゃんけん大会。今年は多くの賞品が用意され、支部メンバーも多くの人が賞品をゲットすることができた。最後は全員で山に関係する歌を歌い、今年のイベントは終了した。ご参加いただいた皆様、ご協力ありがとうございました。 (神谷敏裕)
山行記録に戻る
46.奥武蔵/入間川沿いの彼岸花を楽しむ
期 日:9月25日(木) 日帰り 晴時々曇
参加者:L佐藤邦弘、SL上野進、中村公子、岩井初江、北原 好、黒澤寿子、助廣弘子、英賀昇子、中村博雄、飯嶋光江、古川泰子、近藤由美子 計12名
コース:西武鉄道飯能駅南口10:15=前ヶ貫入口バス停10:24―清川橋10:30―成木川沿い―新大橋10:53―加治橋11:04―入間川沿い―真善美の小径11:11―JR八高線下―阿須運動公園―トーベ・ヤンソンあけぼの子どもの森公園(昼食)12:18~50―阿須山13:29―下山14:08―阿須運動公園―入間川沿い―上橋14:38―円照寺14:44―西武鉄道 元加治駅15:05
前ヶ貫入口バス停で我々のグループ12人が降りると、残ったお客は1人のみ。いつもがら空きの状態で走っているバスなのだろうか。減便や路線廃止が気になってしまうこの頃だ。
バス停から青梅市の黒山が源流だという成木川に向かう。今回訪ねる2か所の彼岸花群生地のうちの一つ。途中で道路脇に鮮やかな彼岸花のかたまり。期待が膨らむ。成木川に架かる清川橋を渡って左岸に降りると、少し先に真っ赤に燃える彼岸花の群生が目に飛び込んできて、思わず感嘆の声。上流に向って桜並木があり、その下一面に彼岸花の群生地が広がる。全面が真っ赤に染まるのは二、三日後か。歩く道の両脇はちょうど満開だ。脳裡から消し難い鮮烈な色。カメラを持った男性が一人。花見客は前情報どおり少なく、儲けた気分だ。「前ヶ貫堰水門移設之碑」の所で道は終わり、引き返す。
気持ちの良い成木川沿いを下流に向って歩く。次に向かうのは2つ目の彼岸花群生地である真善美の小径。異常な酷暑はようやく終わったか。新大橋を渡り、右岸へ移る。いつの間にか成木川は入間川と合流し、加治橋をくぐると土手には桜並木。ほどなくして真善美の小径に。先客のグループがいる。半端でない彼岸花の群生。真っ赤に咲いた彼岸花が、辺り一面隙間なく埋め尽くしているではないか。度肝を抜かれた感じで見とれる。さながら赤絨毯のようというよく見かける表現も悪くはない。「真善美の小径」という名の由来は、すぐそばの加治中学校の校訓で、生徒もここの管理に加わっているとのこと。この日は体育祭に当たっていて、校庭から生徒の熱い声援と歓声が轟いていた。
平坦なコース一本ではあまりに変化に乏しい。加治丘陵の阿須山188.6mに登る計画を加えた。メルヘンチックで異国情緒にあふれた「トーベ・ヤンソンあけぼの子どもの森公園」で昼食した後、公園裏から阿須山に登ろうしたが、2つの登山口には封鎖の表示。他の登山口を探してしばらくウロウロ。公園の関係者に出くわし、聞いてみると、公園の管理下外になり、道が荒れている恐れがあるから、ここから登るならば自己責任と念を押される。了解して登り始めると思わぬ急登に緊張を強いられる。封鎖のわけもうなずけるというもの。紛らわしく道がいくつか現れ、方向だけを頼りに進む。やがて東屋が建つ高みに。そこには二等三角点と阿須山山頂を示す古びた標柱。樹木に囲まれて展望はなく、静寂さが漂う山頂だった。
下山して運動公園を抜け、再び入間川沿いに戻り、のんびりと歩いてゴールの元加治駅へと向かう。振り向けば、ひと際目立つ高層の駿河台大学。上橋を渡るとすぐ先に最後の立ち寄り場所の圓照寺。広々とした境内。そして趣のある蓮の池。ここは入間市。一休みして圓照寺を離れると、元加治駅はあっけないほど近かった。(佐藤邦弘)
山行記録に戻る
47.日光/鬼怒沼、根名草山
期 日:9月27日(土)~28日(日)前夜発一泊二日 晴天
参加者:L小磯登志子、堤理恵子、杉江秀明、矢澤孝二 計4名
コース:バスタ新宿22:40=大清水4:10~5:15-渡渉点6:20~25-物見山(毘沙門山)9:30~50-鬼怒沼山10:55~11:10-鬼怒沼11:50(昼食)~12:20-日光澤温泉15:00(泊)~5:05-手白沢分岐6:40~50-根名草山9:05~20-念仏平避難小屋10:15~25-温泉ヶ岳11:40~45-金精峠12:35~40-金精トンネル駐車場13:10~24-沼田駅15:20
費 用:バスタ新宿=大清水 尾瀬号5,000円、金精トンネル駐車場=鎌田=沼田駅2,148円+1,749円
日光澤温泉(一泊夕食付)10,900円+朝弁当600円
金曜日の夜行バス「尾瀬号」で未明の大清水へ。下りたほかの乗客は、みな尾瀬沼へ向かうようだ。
明るくなるのを待って、われわれは東へ、根羽沢沿いの林道を進む。50分ほどで終点となり、その先で渡渉。尾根に取り付いて行く。アスナロ林をひたすら登って行くが、倒木や張り出した枝、不安定な足元など結構タフな急登の連続だ。ようやく前方に日が昇ってきた。処々ダケカンバも見られるが、総じて暗い登りが続く。
何回かの小憩を挟み、ようやく高くなると、右側にずんぐりした独立峰が見えて来た。あ、男体山だと思ったが、後で日光白根山だと判明。90度違うのに、登るのに一所懸命で方角を意識できておらず反省。やっと傾斜が緩み、上部が明るくなって木々の合間に空が見え、物見山に到着。樹林に囲まれた静かな山頂だったが、燧ヶ岳と尾瀬沼が望まれた。
反対側に下って鬼怒沼山に登り返し、再び戻って鬼怒沼湿原に出る。草紅葉が始まって、湿原全体が赤茶色に覆われている。目の前には白根山(ここで判明)、その左に明日歩く根名草山と温泉ヶ岳が大きく続く。池塘はその稜線を、さざ波も立てず、静かに映していた。ゆっくりと昼食。今年初めて感じる秋。この静かな湿原は、時間をゆっくりと流してくれていた。
その湿原が尽きて、下りにかかる。こちら側から登る人が多いようで、道もしっかりしていた。アスナロ林を下っていくと次第に沢の音が聞こえ始めた。ずいぶん下って、オロオソロシノ滝展望台になる。谷を深く挟んだ向こう側に大きな滝が懸かっている。深い原生林の中、悠久の流れがそこにあった。
そして深かった谷間まで下りと、奥鬼怒温泉郷の最奥、日光澤温泉に到着。白濁した源泉の露天風呂で、ゆっくりと汗を流す。夕食には期待した岩魚の塩焼きも出て、早めに就寝したのだった。
翌日も足元が見られるようになってから出発。今日もアスナロの急登だが、ジグザクに切ってあるので登りやすい。背後の沢音が遠ざかって、手白沢温泉分岐。風が冷たい。ここから稜線の左側を巻く道を進む。途中ガレ場が3ヶ所あり、コメツガやシラビソの植生になって鞍部に出ると、笹の登りとなる。山頂直下、右手に山上の湿原が見える。鬼怒沼だ。その湿原はここから見ても、森林の中に際立って赤茶色が目立っていた。
根名草山に到着。白根山がボウっと見え、笹を揺らす風の音だけの静かな山頂だった。
この先、金精峠から往復する登山者が多くなる。とは云っても道には笹が被り、泥濘も多い。念仏平の避難小屋は新しくきれいで、20人くらいは泊まれそうだ。水場は15分くらい先だったが。
左側に切込湖や戦場ヶ原が見えて来て、一番ササヤブが酷い斜面を通過、温泉ヶ岳へ分岐から往復する。辺りの紅葉は、昨日よりも進んでいる感じがした。
金精峠からの下りはハシゴや鎖の連続で、思いのほか時間がかかったが、ようやくトンネル入口の登山口に下り立つ。10分で湯元発のバスに乗り、鎌田で乗り換えて沼田に向かった。
歩き甲斐のある秋の縦走だった。(矢澤孝二)
山行記録に戻る
48.箱根/十国峠(771m)(花山行)
期 日:9月28日(日) 日帰り 晴れ
参加者:L安瀬はる江、SL大貫文正、森田隆仁、助廣弘子、黒澤壽子、鎌田文子、若松節子、白石克人、瀧沢正明、中村博雄、岩井初江、伊藤和良、要加月、黒川恵理子、星野ゆかり、高木千代 計16名
コース:湯河原駅8:40=タクシー=十国峠登山口8:55~9:20―508m休憩10:05~15―岩戸山分岐11:00―東光寺11:05~10―十国峠11:35~12:05―石仏の道分岐12:35―舗装道13:30―西山バス停13:50~14:05=バス=熱海駅
タクシー代 600円/一人
天候の好転を辛抱強く待って、晴れの一日に恵まれた。集合に一人遅れたが、携帯で交信して、無
事に合流できた。十国峠は箱根外輪山から続く尾根の一部で、古くは日金山として知られていた。その後十国五島の景勝地として、更に文学作品等には十国峠と称され、その名が普及したと聞く。
最初は暗い林の中、丁目石を目当てに歩を進める。沢沿いになると、大量に繁る葉の中に咲いている花があり、その数は極僅かだった。思いがけずオトメアオイにも出合えた。沢から離れると、笹に覆われた登りを岩戸山分岐まで熟す。丁目石は40丁目だった。その先の東光寺に立ち寄りお礼参りをする。
左に姫の沢公園入口を見てから、右の霊園内に入り込み、急な階段で登山道に戻った。360度展望のある十国峠は広い円形状で、展望台が建つ。大勢の人が思い思いに過ごしていた。ベンチにもなる斬新な設備が増えて、ゆっくり昼食が摂れた。雲が広がり、富士山始め遠望はなかった。東側の海面には長い房総半島が横たわり、伊豆の山々は指呼できた。
下山にとった「石仏の道」は花盛りで嬉しい誤算だった。カヤトの原で、足元も草地で優しい。初見の花や固有種があり、種類も多かった。眼前には大海原が広がり、所々に石仏が鎮座していた。舗装道に降り立ち、続く予定の実線道が通行止めだった。東側の舗装道でいくが、バス停探しに難儀した。やっと辿りつくと予定時刻8分前。解散式をして待つと遅れて来た。静かな山中だったが、バスで到着した熱海駅は混雑していた。
山行中の花々、コクラン実、ヤマジオウ葉、ミヤマシキミ実、アケボノシュスラン、オトメアオイ、カントウカンアオイ葉、ホトトギス、ハキダメギク、シュウブンソウ、キバナガンクビソウ、ミゾソバ、ゲンノショウコ、イヌゴマ、シロバナマンジュシャゲ、シソ、タムラソウ、ヤマハッカ、ヒヨドリバナ、ソバナ、ツリガネニンジン、ヤマラッキョウ、アキノキリンソウ、イズコゴメグサ、ソナレマツムシソウ、マルバハギ、キハギ、オミナエシ、トネアザミ、アキカラマツ、シロバナヤマハッカ、シロバナソバナ等(安瀬はる江)
山行記録に戻る
49.越後駒ケ岳、平ケ岳
期 日:10月4日(土)~6日(月)二泊三日
参加者:L萩原克己、SL神谷敏裕、岩井初江、北原好 計4名
コース:
10月4日(土)小出駅 ホテルオカベ泊
10月5日(日)霧雨~曇
ホテルオカベ=枝折峠4:35-明神峠5:05-小倉山6:46-駒の小屋8:40~8:53-頂上9:07~9:30-小倉山11:52-明神峠13:36-枝折峠14:00-15:30湖山荘(泊)
10月6日(月)小雨~曇~晴
湖山荘3:45=中ノ峡登山口5:00~5:25-平が岳頂上8:25~8:41-玉子石9:37-登山口11:30=宿13:45=浦佐駅解散
費 用:ホテルオカベ¥7370、銀山平湖山荘、¥65450、レンタカ−&燃料代金¥22650
10月5日 越後駒ケ岳、
霧雨で天気が悪いので滝雲目当て観光客は昨年とは打って変わって少なかったです。
枝折峠を少し登った滝雲のビュポイントがありましたが、肝心の滝雲は見られず奥只見湖が見え大明神の小祠の明神峠に出て霧雨も上がりアップダウンを繰り返して道行山を巻いて駒の湯(50年ほど前に下って泊まって日航の整備社員に初めてバ一ボンを飲ませて貰った)の分岐点の小倉山に着き、ここから少し急な登りになり、駒の小屋のアンテナも見え、直下岩稜地帯の鎖場のある一番の難所を越えると管理人のいる駒の小屋です。
小屋で少しゆっくり展望を楽しみ、もう草黄葉頂上も指呼の間で10分ほどで頂上に着きました。
正面に10年前にYさんと体育の日に荒沢岳〜灰の又山〜兎岳〜丹後山まで11時間掛かった縦走の稜線が見え感無量でした。
駒の小屋でゆっくり食事をして小屋からの下りは慎重に下りました。
宿の車が迎えに来たらちょうど雨が降って来てちょうど良いタイミングでした。
日帰り温泉・白金の湯で疲れを癒しました。
10月6日 平ケ岳
朝から小雨模様で私はあまり登る気はしなかったのですが(5年程前は雨で登らず仲間は登りました、昨年は東京支部、武蔵野支部の女性を連れて、神谷さんの弟さんが偶然同じ宿に泊まり彼と八海山の一升瓶を飲み宿の主人に?)、皆さんは初めてなので登らないと何を言われるか?
歩き始めて直ぐに沢を渡るとヒカリゴケの群生地があり、いきなり急こう配になり、先が思いやられましたが、1時間ほど登ると樹齢1000年以上のクロベの大木があり、心が癒されます!。
辛抱して登って行くとあと70分で玉子石と貼り付けがあり、また1時間ほど直登が続き稜線に出ると行く手の平が岳の方向はガスってて木道の緩い登山道を黙々と池塘の間を縫って行くと何人かの人が見えてそこが頂上でした。
霧で周りの景色が見えませんでしたが三角点を確認し、食事をして玉子石迄下るとガスがあっという間に切れ、青空の紅葉が見えたので、近くの展望に効く玉子石迄行くと先に下って行った人も何人か戻って来て暫し景色を堪能していました。
願わくば頂上で晴れてくれれば良かったのに!
下山したら宿の主人たちが作ってくれたキノコ汁を御馳走になりました。
私は鷹ノ巣コ一ス2回と残雪期1回の登っていますが、このコ一スは短時間で登れますが一番味気ないル一トですね!
これから平ケ岳を登りたい人は鷹ノ巣コ一スで登ってもらいたいですね!(萩原克己)
山行記録に戻る
50.三浦/大楠山(241.1m)(花山行)
期 日:10月4日(日) 日帰り 晴れ
参加者:L安瀬はる江、SL繁村美知子、黒澤壽子、鎌田文子、近藤由美子、松本悦榮、若松節子、高木千代美 計8名
コース:逗子駅9:05=バス=前田橋バス停9:30~35―お国橋9:40―前田川遊歩道―尾形瀬橋10:00―花観察11:00~50―大楠平12:05~40―花観察12:45~55―花観察13:30~40―古道入口14:05~30―佐島入口バス停15:00~13=バス=逗子駅
花の開花状況により、やむなく2週続けての計画になった。当日は曇り予報が晴天になり、暑い一日だった。お国橋手前で、前田川を遡行できる遊歩道に下りる。川を右に左に渡渉しながら行く一興のある道だ。前日の雨で飛び石が滑り易く、慎重になった。続く登山道も滑り易かった。花探しで足元ばかりを見て、樹林の状況は疎かになり、記憶が薄い。途中で花を撮影している方に出くわし、開花場所を教えて頂いた。1㌔程の道のりに点々と咲いていた。時間を忘れ、みんなで探し合い、撮影をしながら歩く。50分はかかっていた。
大楠平の展望台階段の日影で昼食。帰りは長坂に行く古道を辿る。全員一致で大楠山山頂は巻く。塚山公園コースに入り、ゴルフ場脇を過ぎ、衣笠山公園コースも分岐する。こちらでも珍しい花々に出合えた。この古道は両脇鬱蒼とした藪や照葉樹が続く。展望はなく、無風で汗ばむ。花も途切れ、足並み揃えて、黙々と歩く。古道入口で芦名にでる近道を行く。すぐに藪が深くルートを見失い断念する。当初予定の南葉山霊園の脇を長坂に向かう。集落の野菜直売場も利用でき、ゴールの佐島入口バス停へ。前のコンビニで飲み物を調達。束の間の打ち上げをして、バスに乗り込めた。
山行中の花々、ノコンギク、クコ、コクラン実、スズメウリ、キツネノマゴ、ゲンノショウコ、クサフジ、クズ、フユノハナワラビ、アザミ、ヤブラン実、シロヨメナ、ウスバスナゴショウ、ツルボ、カゲロウラン、ノササゲ、カラスウリ、クワ葉、ヨツバムグラ、ヤブマメ、ツリガネニンジン、ヌマダイコン、ナチシダ、イヌホウズキ、クサギ実、マルバノホロシ実、オオシマシュスラン実、マンジュシャゲ等(安瀬はる江)
山行記録に戻る
51.多摩/鶴見川源流とその周辺を歩く(その1)
期 日:10月18日(土) 日帰り 晴時々曇
参加者:L佐藤邦弘、SL大貫文正、白石克人、森田隆仁、井口良子、鎌田文子、北原 好、中村公子、中村博雄、岩井初江、助廣弘子、附田京子、矢澤孝二、松宮俊彦 計14名
コース:JR 淵野辺駅北口9:50=平バス停10:00―谷戸の畑10:18―尾根緑道―上小山田池谷戸児童公園10:30―池谷戸バス停―小山田1号遺跡10:38―神明神社10:55―養樹院11:13―上小山田みつやせせらぎ公園―野中谷戸11:46―鶴見川源流保水の森(昼食)12:10~30―鶴見川源流の泉12:45―芦田谷戸13:00―尾根―畑13:19―南大沢バードヒルズ―トバ谷戸―小山田バス停14:05
町田市北部の鶴見川源流とその周辺は多摩丘陵の地形が残り、緑が多く近場の軽ハイキングには打って付けだ。小野路・図師地域はよく歩かれているので、比較的マイナーな上小山田地域をメインに2回に分けて歩く計画を立てた。今回はその1回目である。
バス停を降りると、道端に無人の農産物販売所。他の品は売り切れたのか、サツマイモのみが置かれていた。新しい住宅が建ち、ご多分に漏れず宅地化の波が押し寄せている町田市北部であるが、山林が残り、点在する農家の庭には柿の木が目立ち、柿の実はみな鈴なり。まさに半端でない。そのまま放置されているところを見ると、渋柿なのだろうか。のどかな秋の田園風景だ。
谷と尾根でつくられた丘陵地。谷や斜面は農地に利用さて、田畑が広がり、尾根に上がると見晴らしがすばらしい。高低差があるので、下ったり上ったりで脚力も必要だ。室町時代の有力武士の館であったという小山田1号遺跡。丘の頂上には立派な神明神社。寂しげな森のなかの養樹院。鐘楼には釣鐘がなく、処理されることなく倒れた木があった。
北へ進み、正山寺の傍らの尾根を歩く。林のなかの道は立入禁止のガードが左右に連続して設置され、いささか興醒めだ。ガードが切れて、明るくなった尾根から眺める谷戸の佇まいが美しい。左に戻るように降って野中谷戸に。田園風景全開といったところ。空を見上げると青空にウロコ雲が広がる。一人のおばあさんがクワを使って黙々と作業している後ろ姿がなんとも印象的だ。広々とした野中谷戸を抜けて源流保水の森へ。自然豊かな空気を満喫。
鶴見川源流の泉を見て、開放的な芦田谷戸へと入る。ここから尾根道を辿って谷戸を脱出する計画だ。尾根の入口にはなんと倒木。最近は人が歩いていない形跡。何とか倒木を持ち上げて、尾根に取り付く。道ははっきりしているが、竹林で藪化が著しい。先頭を行く超ベテラン森田さんのお陰で登り切り、出口の高台の畑に出て一安心。ゴールに近いトバ谷戸の御休み処でバス時刻には間があり、時間調整。里山歩きとはいえ、急に疲労感が。
異常な暑さが続いた今夏。秋は確実にやってきているようだ。この日はまだ汗ばむ気温であったが、気温も下がって、動きやすい絶好のハイキング日和が待ち遠しい(佐藤邦弘)
山行記録に戻る
52.青森/岩木山、八甲田山
期 日:10月17日(金)~19日(土) 17日:曇り一時小雨、18日:曇りのち小雨
参加者:L神谷敏裕、山口音子、中村和江、要 加月 計4名
コース:10/17(金)弘前BT7:10=岩木山神社前8:10~8:20-百沢コース登山口8:45-カラスの休み場9:28-姥石9:50-焼止りヒュッテ11:00-種蒔苗代12:30~12:50-鳳鳴ヒュッテ12:55-岩木山山頂13:20~13:40-鳳鳴ヒュッテ14:00-岩木山山頂駅(八合目)14:35~15:45=嶽温泉16:15~16:20=弘前駅前17:20 東横イン(泊)
10/18(土)弘前7:06=青森7:46~8:10=酸ヶ湯温泉9:15~9:40-仙人岱11:15~11:25-酸ヶ湯温泉12:55(泊)
10/19(日)酸ヶ湯温泉8:50=青森駅9:35~9:52=新青森9:56
費 用:弘前BT~岩木山神社前500円、岩木山山頂駅(八合目)~岳温泉1,200円、
岳温泉~弘前駅前500円、弘前~青森680円、青森駅~酸ヶ湯温泉1,570円
10/17(金)岩木山:前夜泊組と夜行バス組が弘前で合流。バスターミナルと駅前バス乗場があるため、お互いが出会えず朝からちょっとしたハプニング。岳温泉行きのバス内で合流し、岩木山神社前で下車。岩木山神社で登山の無事を祈願。神社横から歩き出す。桜林公園を抜けスキー場まで登ると、ゲレンデ脇から登山道が始まる。七曲りが急坂だが、その後は暫く比較的緩やかな坂が続く。焼止りヒュッテを過ぎると岩が多くなり谷筋の急登となる。焼止りヒュッテ手前から小雨が降り出したが、急登に入ると雨は止む。中腹から上は紅葉がピーク。山頂直下も岩の間をぬって急登を登る。頂上からは遠方は見えないものの、紅葉に染まる麓や日本海側の海岸線などが雲間から垣間見えた。嶽温泉に向けて下山。十分歩いたとのメンバーの意見もあり、8合目まで下りて岳温泉まではシャトルバスで下山。岳温泉でバスを乗り継いで宿泊する弘前に向かった。弘前では地元の人が集う居酒屋れんが亭で反省会。
10/18(土)八甲田山:朝、列車で青森に移動。青森駅からはバスで酸ヶ湯に向かう。紅葉時期のため乗客が多くバスの増発があった。酸ヶ湯温泉に不用な荷物を置かせて頂き、時折、薄日がさす中、出発。酸ヶ湯温泉付近が丁度紅葉真っ盛り。紅葉のトンネルの中を緩やかに上っていく。地獄湯の沢を登って行くと強い風が吹き始める。西には怪しげな黒い雲。登り終わると雨がポツポツ降り始める。仙人岱を歩いて行くと小岳が正面に見えるが大岳は雲の中。下山者に聞くと大岳山頂は強風でかなり寒いとの話。更に午後は雨予報のため、仙人岱で下山を判断。仙人岱ヒュッテまで行って身支度を整え小雨の中、来た道を戻る。
宿に着いて寛いでいると外は土砂降り。早めに着いたのでチェックインまで温泉、土産選びなどで過ごした。チェックイン後は有名なヒバ千人風呂に浸かり、2日間の疲れを癒した。翌日は寒冷前線通過後で朝からかなり寒い。帰りは宿の送迎バスで青森駅に行き解散した。
雨模様で八甲田山の頂は踏めなかったが、紅葉を満喫した山行だった。(神谷敏裕)
山行記録に戻る
53.奥多摩/檜原村山中に民家を訪ねる
期 日:10月29日(水) 日帰り 晴時々曇
参加者:L佐藤邦弘、SL森田隆仁、若松節子、中村公子、鎌田文子 計5名
コース:武蔵五日市駅10:06=藤倉バス停10:53―春日神社11:10―旧藤倉小学校11:15―旧小林家住宅12:02~13:05―小河内峠分岐―田倉家住宅13:20―往路戻る―小河内峠分岐13:40―陣馬尾根合流14:15―旧藤倉小学校14:40―藤倉バス停14:55~15:32―武蔵五日市駅16:20
武蔵五日市駅バス停からバスは我々5人を含め10人の客を乗せて、市街地を抜け、あるき野市から檜原村に入る。数人の乗り降りがあったが、笹久保バス停で1人が降りると我々だけ。山あいの道路はきれいに舗装されているが、すれ違う車もなく、檜原村の奥であることを印象づける。約50分を要して終点の藤倉バス停に到着。ここは東京都。シルバーパスを見せて下車した。
計画は春日神社・旧藤倉小学校を経由して古民家「小林家住宅」に至るルート。バス停から直ぐのショートカットの階段を利用して春日神社への舗装道路を登って行く。神社には杉の巨木がそびえ立ち、迫力十分。集落の鎮守として信仰を集めてきた雰囲気が漂っている。隣の小高い場所には昭和61年(1986年)に閉校した旧藤倉小学校。小さな小さな木造平屋の校舎だ。入口のガラス戸をそっと開けてみると部屋から人の話し声。残された校舎はNPO法人によって運営されているというから、会議でもしているようだ。
小林家住宅への山道は簡易舗装されていて、しばらくは角度のある急坂が続き、高度をぐんぐんと稼ぐ。小河内峠分岐を過ぎるころから、道は傾斜が緩み、立派な茅葺屋根の小林家住宅に導かれた。先客の姿が数人。どうやら車で来て、モノレールを利用してここまで上がって来たようだ。標高約750m、山々に囲まれた奥地の空間。南面が開け、視界が広がる。紅葉にはまだ早いようだ。背後の山の緩斜面はたくさんのミツバツツジ。ベンチもある。管理棟があり、ここの管理人の方で、いかにもやさしそうな白髪のおじさんが迎えてくれて、レクチャーもしてくれるという。とりあえず、腹ごしらえ。日当たりのよい南の縁側にのんびりと腰かけて弁当を広げた。
昼食後、広々とした屋内に上がり込み、台所や広間を見学。そして板の間に座り、管理人の説明を受ける。建てられたのは江戸中期の1700年ごろ。昭和53年(1978年)に国の重要文化財に。屋根は入母屋造り。くぎは使われていない。昔から炭焼きが行われ、明治になって養蚕も。15年ぐらい前に約4年かけて、解体修理され、70%は元の材料、30%は新材。解体する前は実際に人が住んでいたなどの話を伺った。終始にこやかに話す姿が印象に残る。
さらに山奥の旧田倉家住宅へ向かう。小林家住宅から北へ約15分。標高約800mに建つ。とがった屋根下に大きなスズメバチの巣。庭からの眺めがよい。杉の巨木の根のところに「大杉の泉」と名付けられた湧水があり、澄んだ水を湛えていた。荒れ果てた様子はなく、管理がなされているようだ。
旧田倉家住宅から小河内峠分岐まで往路を戻り、枝尾根を標高100m程度登って、広い陣馬尾根に合流。ここから下山開始。土の山道は足にやさしいフカフカの道。しばらくはルンルン気分で降ったが、往路の道に合わさり、急坂は往路とは逆に激下りに転じ、足にこたえた。
神々しく山々が連なる檜原村の藤倉集落。この地で暮らす人は減ったが、山中には風雪に耐えた石仏や空き家らしき家がポツリポツリとあった。かつて営まれてきた山の暮らしの面影を感じ取ることができて、妙に気持ちが落ち着いた。(佐藤邦弘)
山行記録に戻る
54.奥多摩/棒ノ折山~岩茸石山~高水山
期 日:11月1日(土) 曇り時々晴れ
参加者:L神谷敏裕、SL大貫文正、水内好江、瀧沢正明 計4名
コース:飯能駅8:00=さわらびの湯8:41~8:50-白谷橋9:15-岩茸石10:30-権次入峠10:50~10:53-棒ノ折山11:08~11:25-権次入峠11:38-黒山11:58~12:18-岩茸石山13:50~14:05-高水山14:30~14:37-常福院14:45~14:50-高源寺15:37-軍畑駅16:02
東飯能駅からバスに乗る予定にしていたが、駅前のバス停に行くと飯能祭りのためルート変更となっておりバスが来ないことがわかった。飯能駅に移動し30分後のバスに乗車。さわらびの湯は人が多いところだがこの日はひっそり。公衆トイレの前で山行計画書提出の呼びかけがあり、記入するとエマージェンシーシートなどの記念品をもらうことができた。スタート後は車道を上がり、名栗湖のダムを渡って30分弱で登山口に到着。白谷沢沿いに渡渉を繰り返しながら登っていく。沢の後半は鎖、ロープを頼りに登る所も。岩茸石からは階段などを登り権次入峠へ。更に登っていくと棒ノ折山の山頂に到着。近くは秩父の山々、遠くには谷川岳、筑波山などが望める。山頂付近はススキの穂が開き、紅葉も進んでいた。山頂から権次入峠まで戻り、今度はアップダウンを繰り返しながら岩茸石山に向かう。8年前に歩いた道だが、前回よりきつく感じる。歳のせいか。。岩茸石山の山頂からは歩いてきた尾根が見える。最後は高水山。山頂はあまり見通しなし。花の百名山と記載があったが、季節が外れているのか花は何も見つからなかった。少し下ると立派な境内の常福院。ここを過ぎるとひたすら山道を下っていく。高源寺の手前から民家がちらほら。車道を30分弱歩くとゴールの軍畑駅。スタートは30分遅れだったが、健脚揃いで日暮れ前に到着することができた。 (神谷敏裕)
 白谷沢沿いに登る |
 鎖、ロープを 頼りに登る |
 渡渉を繰り返す |
 立派な岩茸石 |
 棒ノ折山の 山頂にて |
 山頂から 秩父の山々 |
 御岳山方面の峰を望む |
 岩茸石山の 山頂にて |
 歩いてきた 棒ノ折山 |
 高水山の山頂にて |
山行記録に戻る
55.山形南部/置賜(おきたま)地域の里山低山を巡る
期 日:11月5日(水)~7日(金) 二泊三日 晴 晴時々曇 曇時々晴
参加者:L佐藤邦弘、SL大貫文正、高木弘司、若松節子、本山まり子、後藤勝弘、上野 進、伊藤有子
黒澤寿子、北原 好 計10名 ※若松、本山は三日目不参加
費 用:宿泊料(飲食代含む) 270,601円、ジャンボタクシー料金 4,960円
コース:一日目:羽前小松駅11:00―常念寺―大光院 仁王門―鏡沼―川西町浴浴センター まどか-高戸屋山西回り入口11:45―展望地(昼食)12:20~12:50―分岐―内山沢堤・東屋13:45―高戸屋山(368m)14:08―高戸屋山東回り入口15:26―川西温泉「川西町浴浴センターまどか」15:45(泊)
二日目:川西町浴浴センター まどか8:25―原田城址―9:10羽前小松駅9:22=南米沢駅9:50―堀立川―幸徳院・笹野観音堂10:35―中の道分岐11:14―笹野山峠11:14―笹野山(660m)12:19―斜平スカイツリー(634m)昼食12:36~13:00―新奥の細道―愛宕山・愛宕神社13:38―片倉山コース―分岐14:20―徒渉14:40―日本芸能神社、愛宕羽山両神社14:43―西明寺―15:21舘山一丁目バス停15:46=小野川温泉バス停15:56―小野川温泉「湯杜 匠味庵 山川」16:00(泊)
三日目:小野川温泉宿8:25―小野川温泉バス停8:45=9:10米沢駅前9:20―普門寺9:30―舘山10:20―梓山栗子山展望所10:30―早坂山最高点(508m)10:50―屏風石上展望所11:13―早坂山(502)m11:25―反射板11:47―展望地11:53―車道12:10―蛙石山12:15―下山口12:30―S(株)1号館前12:45=JR米沢駅13:00
山形県の南部に位置し、置賜地域と呼ばれる川西町、米沢市の里山低山を3日間にわたって歩いた。歩いた山はいずれも地域住民に親しまれている里山低山との事前の情報どおり、温かい手が入れられ、必要な箇所には道標があった。東北の黄葉見たさにこの時期を選んだが、三つの山すべて、入山してから下山するまで、山は黄金色に輝く黄葉に包まれ、贅沢で至福の時を過ごすことができ、まさに黄葉三昧の山旅であった。
今回特に注意したのは、例年に較べ、クマの出没と被害の多さ。山形県はクマ出没警報発令中で、ホイッスルで大きな音を鳴らし、遠くまで響かせて進んだ。その効果があったのかどうか、幸いクマと遭遇することはなかった。クマを警戒してか、三日間とも山中で他の登山者と出会うこともなく、結果的には山と黄葉を独占的に楽しんだ。まさに強運に恵まれたというべきか。
一日目の高戸屋山はダリヤの里川西町に位置し、麓には宿泊する「川西町浴浴センター まどか」があり、登るには好条件。隣接の川西ダリヤ園は閉園し、ダリヤはすでに茎が切り取られて、花はなく根元だけ。荷物の一部を「まどか」に預け、西回りで登り、周回することに。道標は完備して道巾は広く、全体的になだらかなコース。開けて展望が広がるところが数箇所あり、冠雪の大朝日岳、三角にとがった山容の祝瓶山などの朝日連峰、そして飯豊連峰、蔵王も見える。赤松が多く松茸が採れるようで、無断入山罰金の表示が目に付く。山頂に登りきる前に尾根を降り、内山沢堤に行ってみる。大きなため池のようだが、湖水のように周囲にマッチし、良好な景観つくっている。高戸屋山山頂からの見晴らしは乏しい。厳しい急坂はなく、もみじ狩りを楽しんで下山。初日の足慣らしには手頃な山であった。
二日目は米沢市の西に位置する斜平山(なでらやま)。斜平山とは5つの峰からなる山々の総称で、最高峰は笹野山。羽前小松駅から南米沢駅に移動。駅から歩いて先ずは笹野観音を目指す。山々に囲まれた盆地に水田が広がり、空は青く朝日が射して幻想的な雰囲気の中を行く。目の前に斜平山が延びている。分厚い茅葺き屋根の笹野観音堂。その造りは重厚壮大だ。ここから笹野山まで林道が通じていた。
青空に映える色鮮やかな黄葉。テレビアンテナが建ち、広い笹野山山頂。何とも気持ちよい稜線を歩いて、360度の眺望地点、斜平スカイツリー(東京スカイツリーと同じ364mの高さからこの名が付く)に。飯豊連峰、朝日連峰、吾妻連峰、栗子連山、米沢市街を一望。腰をおろしてランチタイムだ。稜線の分岐は鎖のある急斜面を降る峰の道は避け、新奥の細道ルートを選択。愛宕山・愛宕神社からは一挙に降る片倉山ルート。降り始めは道形不明瞭だが、次第にはっきりとしてくる。ホイッスルの音が鳴り響く。目をみはる黄葉に染まる森を徘徊。片倉山山頂の手前に分岐と道標。左の道を進む。急勾配の道を慎重に降り、小さい沢を渡って登り返すと山麓の日本芸能神社、愛宕羽山両神社は近かった。西明寺を経て舘山一丁目バス停へ。そしてバスで今夜の宿泊場所となる米沢八湯の1つ小野川温泉へと向かった。
三日目は米沢市の東部に位置する早坂山。昔、山城があったという。小野川温泉からバスで米沢駅に出て、ジャンボタクシーに乗り換え、登山口の普門寺へ。ため池の脇を通って尾根に乗り、高度を上げる。高みに向って直登すると舘山(舘山館跡)の表示。早坂山頂へ55分とある。コース上には道標が随所にあり、「早坂山あるき隊」という団体が整備してくれているようだ。この山も色彩豊かな黄葉の森。冷たい強風が吹き抜け、黄葉の葉が舞い散る。梓山栗子山展望所を通過。早坂山最高点へはキツイ急勾配の登りが続く。とにかく辛抱。トラロープが頼りになる。城跡の堀切がある。北面が開け好展望地の屏風石上展望所で一休み。展望図があり、月山や蔵王連峰が望める。少し先が二等三角点のある早坂山山頂。展望は不良。
滑りやすい急斜面を慎重に降る。気が抜けない。電波反射板が現れる。展望地に立ち寄って、分岐を降ると谷筋の道で車道に飛び出した。早坂山はアップダウンのあるピリリと辛い里山だった。ここから最終目的地の蛙石山(びっきいしやま)はすぐ。高さ約6mの蛙石と名付けられた奇岩と対面。後は北西に降るだけ。無事下山して、S(株)1号館前からジャンボタクシーで米沢駅に向かい、三日間の里山巡りを終えた。(佐藤邦弘)
山行記録に戻る
56.奥秩父/黒富士、羅漢寺山
期 日:11月8日(土)~9日(日)一泊二日 11/8晴れ、11/9曇り
参加者:L神谷敏裕、堤理恵子、中村和江、杉江秀明、瀧沢正明 計5名
コース:8日 町田駅6:30=マウントピア黒平10:00~10:05-ホウズキ平10:50-黒富士峠11:55~12:15-升形山12:35~12:45-黒富士13:10~13:25-黒富士峠14:18~14:25-ホウズキ平15:20-マウントピア黒平16:00
9日 マウントピア黒平=金桜神社-夫婦木神社=仙娥滝駅=パノラマ台-羅漢寺山-パノラマ台=仙娥滝駅-仙娥滝-仙娥滝駅=町田駅
費 用 マウントピア黒平 11,000円(キャビン、5人定員)+暖房費540円 ロープウェイ1,500円(往復)
11月8日
交通が不便なため自家用車を利用。昇仙峡、荒川ダムを通り目的地に向かおうとしたが落石のため通行止め。一旦戻って、金桜神社の手前から林道に入り宿泊するマウントピア黒平へ。駐車場に車を止めてコテージ脇から山道に入る。紅葉真っ盛りの谷筋を沢に沿って登っていく。鹿の広場を過ぎ、黒富士峠に上がる手前は踏み後が殆どなく急登のためジグザグに上っていく。黒富士峠からは八ヶ岳の峰々がよく見える。歩きやすい尾根を進み、急登を登ると升形山。やや雲がかかってはっきり見えないが金峰山、瑞牆山方面が見渡せる。一旦下って更に進み、再び急登を登ると黒富士の山頂。間近に茅ヶ岳、金ヶ岳、遠くには甲斐駒など南アルプスが見渡せる。同じ道を下山。升形山にまた登るのは大変なので八丁平の先をトラバース。回転不足で歩きやすそうな違う尾根に入り込みそうになる。方角を確認したうえで更にトラバース。ピンクテープを見つけて黒富士峠に向かう。峠からはひたすら下山。
宿泊はマウントピア黒平。管理棟には大浴場があり日中の汗を流す。風呂に入った後はキャビンで鍋を囲んで反省会。2部屋ありキッチン、トイレも完備しており、5人いれば1人2千円強で泊れて快適だった。
11月9日
マウントピア黒平を8時に出発。金桜神社前に車を止めて長い階段を上がると境内。夫婦木神社も近いため立ち寄り。参拝を終えて車で昇仙峡へ。ロープウェイに乗車してパノラマ台まで上がる。20分ほど山道を歩くと羅漢寺山。頂上は大きな岩の上で、櫛形山や鳳凰山三山、南アルプス、昨日登った黒富士などが見える。パノラマ台まで戻ってロープウェイで下山。仙娥滝を見学したのち帰宅した。(神谷敏裕)
 マウントピア黒平 から出発 |
 谷筋を登っていく |
 紅葉真っ盛り |
 黒富士峠から 八ヶ岳を望む |
 歩きやすい尾根 |
 升形山から 金峰山方面 |
 升形山から 慎重に下りる |
 黒富士山頂にて |
 金桜神社にて |
 羅漢寺山。 遠くに黒富士 |
山行記録に戻る
57.房総/大福山、笠森観音
期 日:11月14日(金)~15日(土) 一泊二日 晴
参加者:L堤理恵子、SL矢澤孝二、杉江秀明、助廣弘子、本山まり子、油田まり子、横川芳江 計8名
コース:五井駅9:06=養老渓谷駅10:12~20-女ヶ倉橋10:50-梅ヶ谷渓谷日髙邸跡12:10~35-大福山(白鳥神社)13:30~50.-女ヶ倉橋14:50~55-養老渓谷温泉16:00(民宿さかや泊)=養老渓谷駅7:39=上総牛久駅8:16~20=大庭入口(乳子関池)8:25~30-関東ふれあいの道(120㍍ピーク)9:35~45-笠森観音10:15~12:10=茂原駅12:35
費 用: 民宿さかや 一泊二食10,000円、11,000円+入湯税150円
上総牛久駅=大庭入口(タクシー)3,000円、笠森観音=茂原駅(小湊バス)620円
支部ではあまり計画のなかった房総の山を、千葉県在住のリーダに実施してもらった。
五井駅からの小湊鉄道はディーゼル気動車、車輛も50年前から使われていて、天井の扇風機が懐かしい。養老渓谷駅は木造で、昭和3年の造りとのこと。歴史を感じる。
民家の点在する里道を抜け養老川を渡り、梅の古木が並ぶ梅ヶ谷渓谷沿いの山道へ入って行く。明治時代、官職を辞した日向出身の日髙誠実なる漢学者が、この地に理想郷建設を夢みて多くの梅を植えたことが由来になっているとのこと。地域の振興に貢献した偉人として顕彰碑もあった。右側には高い崖が迫り、幾重もの地層が剝き出しになっている。確かチバニアンはこの近くだよと口々に話も弾む。その崖は脆いのか、沢筋には砂が堆積している。水量は多くはないが、右左と渡り返しながら進んで行った。
かなり奥まで入った処に、その日髙氏が屋敷を構えた跡が平地として残っており、昼食とする。裏手には池もありカエデに囲まれているが、紅葉にはまだ早く、青々としていた。
沢筋を離れ、ひと登りすると道路に出、白鳥神社の参道になる。すぐ下まで車で入れるので、参拝者も多いようだ。大福山は社殿すぐ裏手の高みだったが、山頂を踏む人は少ないのか、山名板も消えかかったものだった。
山頂から尾根通しに少し下って、先ほどの車道に降り、あとはこの道路を下るだけ。しかし結構長く、アスファルトは脚に堪える。ようやく女ヶ倉橋で朝の道と合流したが、近道の白鳥橋が通行止めとのことで遠回りとなり、やっとのことで養老温泉へ到着。民宿では女将母娘の心遣いと黒いお湯の温泉、そして盛りだくさんの料理は、疲れた皆にとって何よりの癒しとなった。
翌朝は朝食を早く(6時半)お願いして、駅まで宿の車で送ってもらう。駅前のモミジは朝日に映え、昨日より色鮮やかになったように見えた。
上総牛久駅から予約のタクシーで市原市と長柄町の境まで行き、その境界尾根が今日の前半のコースだ。取り付きは溜池である乳子関池の左岸。池畔にはススキが茂り、池に落ちにいよう気を付けて、朝露にズボン濡らしながら進んで行くと、ピンクリボンが右の斜面に、わずかな踏跡があることを示している。半ば強引に掻き上がって尾根に出ると、どうやらルートもはっきりした。
標高100㍍の等高線を挟んで上がったり下がったり、細かいアップダウンが多い。ときどき大きく尾根が振るので、地形図とコンパスで慎重に方向を確認しながら歩いて行く。秋葉山の標識のあるピークに着くと、右から別のルートが上がって来ていて、道形も良くなった。関東ふれあいの道合流地点は、今日の最高点120㍍のピーク。その先は遊歩道になる。途中の展望台に上ると、低い山並みが遠くまで続いていた。
笠森寺の観音堂は大岩の上に建てられた四方懸造で、千年の古刹。お参りのあと穏やかな日を浴びながら、アイスやお汁粉をいただく。最後に鐘楼で鐘を撞いて2日間を締め括り、1日1本のバス停に向かって房総の山を後にした。(矢澤孝二)
山行記録に戻る
58.湘南/酒匂川沿いを歩く (新入会員歓迎山行)
期 日: 11月22日(土) 日帰り 晴
参加者:L松宮俊彦・神谷友子 SL松本悦榮・神谷敏裕、小原紀子 黒澤寿子 竹田早苗 大貫文正 佐藤邦弘 小磯登志子 横川芳江
高木弘司 大槻章夫 太田久枝、宮崎博之 伊藤晃 星野ゆかり 延澤英明 野老真子 附田京子 高木千代美 計21名
コース:
(Aコース)富水駅9:00―二宮尊徳記念館9:20―善栄寺9:50―報徳橋10:15―酒匂川健楽ふれあい広場(きのこ鍋と講話)11:20~13:30―新松田駅14:00(解散、2次会)
(Bコース)国府津駅8:00―風外窟分岐9:00―高山9:30―見晴台9:50~10:05―別所梅林―下曽我駅10:45~11:04=松田―酒匂川健楽ふれあい広場(合流)
費 用:支部予算(8,000円)の補助内
10月実施の予定が雨で順延となり、リベンジとなったが今回は好天に恵まれた。
(Aコース)は富水駅に集合、二宮尊徳の記念館で生家や当時の調度品を見学。いろりでは燻蒸が実演されていた。実物大の二宮尊徳の銅像の高さに驚いたり、色づき始めた紅葉を愛でたりした。尊徳や木曽義仲、巴御前の墓がある善栄寺を経て、酒匂川の堤防に向かう。報徳橋を渡り、酒匂川沿いの直線コースをひたすら歩く。が左手には富士山や明神ヶ岳、金時山など箱根の山々が連なり気持ちが良い。途中のあづま屋で休憩をとり1時間ほどでゴールの河原に到着。そこからは恒例のきのこ鍋を作り出す。ほどなくBコースのメンバーとも合流し賑やかで楽しいひと時はいつも通り。食後は自己紹介と山の講話。今年は松宮さんによる「支部の歴史」と佐藤さんによる「私の山行計画の作り方」で要点がわかりやすくまとめられているレジメ付き。新入会員はもちろん我々にとっても、支部の実績を知り、今後に活かされる実践方法を学ぶ貴重な機会となった。帰りは川を渡って新松田駅にほどなく到着、解散。(神谷友子)
(Bコース)は国府津駅に3人が集合。光明寺脇の半舗装の道を登って行くと尾根になっていき、両脇にはたわわに実ったミカン畑が続いていた。途中ミカン売り場のご夫婦に声がけされ、私設の立派な展望台に登らせていただき富士山や大山、横浜や江ノ島を眺めながらご夫婦としばし歓談。そこからは尾根道が続き登り切ったところで、右側の細い道を入ると高山(246m)山頂で、山名板は無いが二等三角点があった。その後見晴台で休んだ後、曽我の梅林を抜け、下曽我駅に到着。そこから松田駅までは御殿場線に乗り、下車後会場まで歩きAコースのメンバーと合流した。
(2次会)は、任意参加で新松田駅前の居酒屋で16時まで。今日の山行をサカナに話が弾んだ。(松宮俊彦)
山行記録に戻る
59.奥秩父/帯那山~水ヶ森(1553.2m) G4R2
期 日 :11月26日(水)日帰り 晴れ
参加者 : L小磯登志子、SL松本悦榮、安瀬はる江、堤理恵子、杉江秀明、高原春子(支部外) 計6名
コース :山梨市駅8:00=タクシー=アヤメ群落地登山口8:40~50―帯那山9:00―奥帯那山9:11~15―弓張峠(新)10:16―水ヶ森山頂10:55~11:08―水ヶ森北峰11:23―昼食12:15~40―戸谷山13:16~24―洞雲寺14:54=タクシ―=塩山駅15:16
費 用 : ジャンボタクシー代 山梨市駅~登山口 9,080円、 洞雲寺~塩山駅 6,580円
もともとは安瀬さんリーダーの計画だったが体調に不安があるとのことで急遽リーダーを代わっての山行だった。
備不足で心配もあったが、直前に安瀬さんからの嬉しい参加連絡が入り、不安も飛んで元気に出発。山梨市駅に着いた時は山の稜線はガスがかかっていたが、タクシーで上がるにつれどんどん青空が広がってきた。帯那山に着くと甲府盆地は一面の雲海だった。雲海の奥には冠雪した富士山が控えていた。
写真を撮って奥帯那山に向かう。帯那山の三角点はここにあった。続く1400mピークからは明るく伸びやなか防火帯が続いた。弓張峠(新)は林道と近接した場所にあり標識もあったが、弓張峠(旧)の方は標識等はなく踏み跡もほとんど消えていた。峠から水ヶ森までは150mの容赦ない急登が待っていた。登り切った頂上は風が強く早々に北峰に向かう。北峰から先が今回のメインだ。コンパスを振りながら進む。1430mのポコに向かう前にしばし皆でルート確認。ポコから林道に降り立ち1386mに向かう分岐にブルドーザー道が出来ていた。この辺りで風を避けて昼食タイム。
1386mから3つポコを越えれば戸谷山(鳥谷山)だ。広い山頂から北東尾根に進む。1340m辺りから先の尾根が尾根らしくなくてなかなか読めない。皆で慎重にルートを探す。ようやく「ここで間違いない」となり急な下りをジグザグに降りた。樹木の先にゆるやかな尾根らしきものが見えてきた時はホッとした。その先はすんなりと東山中部林道に降り立つことができた。
私を含め皆さん久しぶりのVルートだったようで、地図読みの楽しさを再認識した一日となった。(小磯登志子)
山行記録に戻る
60.駿河・伊豆/浜石岳~薩埵峠、発端丈山
期 日:11月26日(水)~27日(木)一泊二日、晴/曇後小雨
参加者:L萩原克己、SL上野進、大貫文正、大槻章夫、後藤勝弘、飯島光江、黒沢寿子、岩井初江(支部外)、大塚信夫 計9名
コース:26日 由比駅10:29―宿10:45=浜石野外センター11:00~10―浜石岳11:50~12:15―林道14:55―薩埵峠15:15~20―宿16:10
27日 由比駅8:36=沼津駅8:52~9:41=長浜城跡バス停10:20―林道入口10:30―林道終点11:10―登山道出会11:35―発端丈山11:40~45―分岐12:20―長浜バス停12:40~13:29=沼津駅14:07
費 用:宿泊代¥160,360 タクシー代金¥7,200
11/26行動時間が長いので、当初の計画と逆回りで行くことにして、タクシー3台で浜石野外センターまで行く。浜石岳まではぐるっと大回りして山頂に着く。快晴に恵まれ山頂は360度の大パノラマだ。雪を被った富士山や駿河湾が素晴らしい。ここで昼食とする。薩埵峠までは様々な道が交差しているが、道標が要所に有り迷うことは無い。林道出会いまでは小さな瘤をいくつも越えて行く。自然林から孟宗竹の林に変わり、朽ちたモノレールがあちこちに現れる。最後に急こう配を下ると林道に下りる。舗装道路を下って行くが、両側の急斜面にミカンがたわわになっている。ここのモノレールは使っているようだが若い人でないと、とても作業は出来ないだろう。薩埵峠からは旧東街道を宿まで歩く。風情のある景色だ。宿ではお目当ての桜エビずくしと地元のお酒で盛り上がった。
11/27やはり行動時間が長いのと、午後から天気が崩れそうなので、発端丈山をピストンに変更する。大槻さんと大塚さんは登らずに帰宅した。登山口がはっきりしないので沼津駅の観光案内所で尋ねると、長浜城跡バス停で降りるのが良いとのことだった。バス停からすぐの舗装道路を行くと「発端丈山ハイキングコース重須口」の表示があり、間違いないと安心する。右手に城山(じょうざん)の岸壁がみえた。ロッククライミングの聖地らしい。
しばらく行くと左手に林道が伸びており、かなりきつい勾配を林道終点まで登る。辺りを探すが登山道らしきものは無い。キツイ斜面を尾根に向かい150m程直登すると、正規の登山道に出た。ここから山頂まではすぐだった。記念写真を撮りすぐ下山にかかる。小雨が降りだしたキツイ道をロープを頼りにくだり、三の浦長浜バス停に着く。斜め前に「三の浦総合案内所」があり時間を潰せた。アニメの聖地らしい。ここから沼津駅に出て解散した。(上野進)
山行記録に戻る
61.丹沢/新秦野変電所~田原ふるさと公園~葛葉峡谷
期 日:11月30日(日) 日帰り 晴
コース:秦野駅9:10=東田原バス停9:30―文字道祖神―新秦野変電所10:00―左周り周回―朝日神社10:50―文字道祖神・双体道祖神―田原ふるさと公園・源実朝公御首塚―橋―矢ヶ瀧橋―くずは台団地―葛葉峡谷―つり橋―くずはの家・くすのき広場(昼食)12:00~40―ほたるの道―往路戻る―けやきの道―葛葉川の河原―迷走する―くずはの家―金毘羅宮―14:00宮前バス停14:25=秦野駅14:35
参加者:L佐藤邦弘、SL上野 進、杉江秀明、若松節子、高木千代美、助廣弘子、北原 好、中村公子、森田隆仁、英賀昇子、黒澤寿子、榎本美智子、村瀬美枝子、宮崎博之、繁村純夫、星野ゆかり、鎌田文子、近藤由美子 計18名
新秦野変電所周辺はモミジが多く、秦野の一番の紅葉だと書き付けた個人サイトを見たのは5年以上前。いつかその紅葉を見たいと思っていたが、市街地に貴重な峡谷の緑地が残っていることを知り、それらをつないで歩く計画を考えた。新秦野変電所周辺の紅葉はどの程度紅葉が進んでいるのか、ネットで事前に調べてみたが、全くヒットせず、いささか気懸かりな当日だった。
幸運にも空は雲一つない最高のお天気。秦野駅からのバスは次第に高度を上げる。東田原バス停で下車。見上げると雪を戴いた富士山の雄姿。思わず微笑みがでる。ここは標高150m程度。北に向って緩やかな道を上がっていく。青空の下に大山や南稜の高取山が手に取るようにくっきり。秦野変電所の囲む舗装路に出た。期待に応える鮮やかなモミジの紅葉。広大な敷地の変電所周囲を反時計回りに歩く。遠くに相模湾が白く光る。しばしば足を止めて、陽が射して輝きを増すモミジの紅葉に見とれ、そしてカメラを向ける。青い空が一段とその美しさを引き立てる。他の見物人には会うこともなく、ほぼ周回し、満足した気分で変電所を離れた。
滑りやすい急坂を降り、朝日神社に立ち寄る。道路を横断して南下。のどかな農村風景が広がり、大きな富士を望む田園地帯。その一角に田原ふるさと公園。採りたての柿とサツマイモを入手。そば処が人気のようで、大勢の客で賑わっていた。源実朝公御首塚(みなもとのさねともこうみしるしづか)の五輪塔を見て、最終目的地の葛葉峡谷へ向かう。田園地帯を縦断する形で歩き、戸建ての家が整然と並ぶ住宅街へ。正面に富士山を望む住宅街の道路。「葛葉川ふるさと峡谷(葛葉緑地)」と書かれた写真付きの大きな案内板が立つ葛葉峡谷の入口に着く。燦然と輝くモミジの紅葉がお出迎え。葛葉川に架かる「くずはのつり橋」が現れ、住宅地が間近とは思えない渓谷の雰囲気に変わる。自然観察舎「くずはの家」の前の「くすのき広場」はベンチが多数。ここで昼食とした。
引き返して、再びつり橋を渡り、右折して「けやきの道」に。ネットの柵を開け、葛葉川の河原に降り立つ。清流が蛇行し、対岸の崖の部分は地層が剥き出している。地層観察の場所のようだ。あふれる自然。峡谷と名が付くのもうなずけるというもの。ここから徒渉し、対岸の山道を登って金毘羅宮に出る計画。しかし、水量が多くやむなく断念。その後、山道に出るルートを探したが大誤算で迷走し、タイムロスをしでかす。迷走から脱出して帰路のバス停へ。バスはちょうど去った後。次のバスの合間にりっぱな曾屋神社に参詣。文句なしのお天気に恵まれ、なんとも軽やかな気分を残して家路に就いた。(佐藤邦弘)
山行記録に戻る
62.丹沢/畦ヶ丸 (本部合同)
期 日:12月6日(土)日帰り 晴れ
参加者:L神谷敏裕、SL大貫文正、SL松本悦榮、高木千代美、杉山英治、黒川恵理子、山口音子、瀧沢正明、延澤英明、松宮俊彦、支部外5名 計15名
コース:新松田駅7:25=大滝橋8:35~8:50-一軒家避難小屋10:03~10:12-大滝峠上10:55~11:02-畦ヶ丸避難小屋11:45~12:15-畦ヶ丸12:17~12:25-善六のタワ-本棚14:05-西丹沢ビジターセンター15:00~15:40=新松田駅16:49
前日になって12/6からバスが冬ダイヤに変わることがわかり、慌てて参加者に出発時間が20分早まることを連絡。バス会社の時刻表、乗換案内アプリとも古いダイヤのままで、バスに乗り遅れるところだった。(バス会社ホームページの新着情報に記載あり) また当日はバス利用者が多いにもかかわらず増便がなく、谷峨駅から乗車予定だった参加者は満員で乗れず不参加となった。
大滝橋でバスを下車し14名で出発。落ち葉が積もる山道を、緩やかに大滝沢沿いに登っていく。一軒家避難小屋を過ぎると沢沿いを離れ、本格的な山道となる。大滝峠上からは勾配がきつくなり階段が断続的に続く。左側には大きな山容の御正体山が望める。富士山は残念ながら雲の中。畦ヶ丸手前で一旦下ると冷たい横風が当たり始める。直下の急な階段を上がると畦ヶ丸避難小屋。かなり冷えるので避難小屋内で昼食。小さいながら綺麗な避難小屋で、トイレも完備していて快適。暫く休憩していると一人の女性が入ってくる。会話すると大滝橋で下車せずに終点まで行ってしまった参加者だとわかる(新松田駅では登山客が多く、参加人数を確認できなかったことが災いした)。ここからは15名で歩く。腹を満たして避難小屋からすぐの頂上へ。あまり眺望はよくなく寒いので、記念撮影をして早々に下山開始。
断続的に階段がある山道で、落ち葉が積もっていて歩きにくい。バスの出発まで多少時間がありそうなので本棚の滝に寄る。暫く行くと渡渉をして右岸沿いに回り込んでいくと見えそうだが、大人数で行くのは難しそうなので滝の手前で撤退。この辺りからは沢沿いに渡渉もしながら下山していく。西丹沢ビジターセンターには予定よりやや早く到着。帰りはバスの増発があるとのことで、あまり混むことなく新松田駅に向かうことができた。 (神谷敏裕)
山行記録に戻る
63.鎌倉/番場ヶ谷~獅子舞谷~西御門
期 日:12月9日(火) 日帰り 曇
参加者:L佐藤邦弘SL上野 進、SL松本悦榮、白石克人、若松節子、岩井初江、北原 好、伊藤有子、繁村純夫、黒澤寿子、鎌田文子、村瀬美枝子 計12名
コース:鎌倉駅東口9:35=泉水橋8:48―明王院9:00―御坊橋9:15―番場ヶ谷入口9:23―番場ヶ谷―獅子舞谷につながるハイキングコース10:45―獅子舞分岐10:56―獅子舞谷10:58~11:17―獅子舞谷分岐11:25―天園11:30―公衆トイレー大平山頂下広場(昼食)11:40~12:05太平山12:08―鷲峰山12:37―今泉台分岐―百八やぐら12:45―朱垂木やぐら13:04―建長寺分岐13:20―西御門―鶴岡八幡宮―鎌倉駅14:00
鎌倉の獅子舞谷の紅葉が美しかった記憶が残っているが、いつのことであったか。その後、体調問題もあり、長い間訪れることなく過ぎて、今回しばらくぶりに実現した。鎌倉の最後秘境と言われる番場ヶ谷の紅葉も気になったので、併せて訪ね、やぐら巡りを後に置いた。
番場ヶ谷に踏み込む前の足慣らしに泉水橋バス停で降りて明王院に立ち寄る。茅葺屋根のお寺は落ち着いた静かな雰囲気だ。遠くから「おはようございます」と住職さんの声。御坊橋を渡り、人家がなくなった地点が番場ヶ谷の入口。ストック、手袋を取り出し、事前の準備。スパッツを付ける人も。吉沢川が流れる脇を突入する。藪のなかに一人ほどが通れる細い道が続いている。川の大きな水たまりを避けて川底を歩き、一旦岸に上がり、再び川底を歩くことを繰り返して上流へとさかのぼる。倒木が行く手を阻む。切り立った崖。荒々しい地層が剥き出しになっているさまはとんでもなく深い谷に迷い込んでしまった錯覚に襲われる。空を見上げる。隔絶されたような世界にきれいな紅葉が現れて、気持ちが和む。最後はイチョウの葉が大量に積もった踏み跡を登ると、獅子舞谷へとつながるハイキングコースに飛び出す。所要時間約1時間30分の秘境探検は無事に終わった。
獅子舞谷に降りる。その紅葉は予想を超えた美しさだった。空は雲が多く、青空と陽光に恵まれることはなかったが、それでも地面は黄色いイチョウの葉で埋まり、緑の空間のなかに赤く柔らかに輝くモミジの紅葉。鎌倉随一との評判に少しも違わずだ。十分に堪能して引き返し、天園ハイキングコースへ。よく知られたハイキングコースだけにすれ違うハイカーは多い。そして大平山の山頂下の広々としたスペースで昼食休憩。他のハイカーたちも昼食場所としていた。
気が付かなければ通過してしまう鷲峰山(じゅぶせん)のピークに登ってみる。何の変哲もないが、木に山名板が取り付けられ、基準点があった。今泉台分岐を左に曲がると、すぐに山の岩壁につくられた多数の洞窟が現れ、圧倒される。百八やぐらだ。やぐらは鎌倉時代中期から室町時代の前半にかけて盛んに造られたお墓。ここから小径を西に進みと朱垂木やぐらと出会う。700年~600年前の歴史的遺跡が何気なく身近に転がっているのが鎌倉なのだろう。静かで雰囲気のよい山道を辿ると十字路。右が大覚池・建長寺だ。左折して西御門地区の奥で海を望む高台に。住宅が建つなかに急勾配の舗装路が下へ延びる。脚への負担を感じ、小さめのジグザク歩行で降る。鶴岡八幡宮を経由し、小町通りに入る。お土産店や飲食店などが所狭しと並び、観光客や若者でにぎわう人気の小町通り。その活気に押されながら鎌倉駅に着いた。(佐藤邦弘)
山行記録に戻る
64.伊豆/遠笠山 (忘年山行)
期 日:12月13日(土)~14日(日) 一泊二日 曇り時々晴れ、雨
参加者:L矢澤孝二、若松節子、杉江秀明、高木弘司、大貫文正、佐藤邦弘、小原紀子、助廣弘子、上野進、後藤勝弘、神谷敏裕、黒澤寿子、鎌田文子、横川芳江、松宮俊彦、附田京子、平山今紀江、宮崎博之、萩原克己、大槻章夫 計20名
コース:伊東駅=遠笠山登山口(ゲート)~-遠笠山~-遠笠山登山口=伊豆高原ユートピア13:55(泊)~9:20=伊豆高原駅9:30~50=熱海駅
今年も伊豆での忘年山行を実施した。
伊東駅からチャーターバスで、天城高原の遠笠山登山口へ向かう。海岸沿いには紅葉の名残が見られたが、標高千㍍を越える高原では、伊豆とは言っても木々は冬の装いだ。遠笠山には山頂にアンテナ施設があるので、今日の歩きは林道だけ。ただしここは宗教法人の私有地とのことだった。舗装とダートが交互の林道だが、地面には落葉が溜まっている。東側に回り込むと、眼下に矢筈山、大室山が見下ろせ、大島が近かった。昨夜降ったものか、道端には雪が少し残っていた。
遠笠山の三角点と標識は木々の間だったので、写真だけ撮ってアンテナ施設横の芝地に移動し、昼食とする。日は時おり射す程度で風があり寒かったが、輝く海には利島、新島が浮かんでいた。天城連峰も目の前で、最高峰の万三郎山にはガスがかかっていた。
順調に登山口に戻り、バスで伊豆高原別荘地の保養所へ。早く着きすぎたし翌日は雨の予報なので、有志で海岸へ往復する。大室山の噴火した溶岩が海へ突き出し断崖を成している「いがいが根」で、しばし打ち寄せる波を眺め、保養所に戻った。
あとは温泉、部屋呑み、夕食そしてカラオケと、いつものコース。9時過ぎにはお開きとなった。
翌日は予報どおり酷い雨。昨日じゃなくて良かったと口々に話しながら、保養所の車で駅まで送ってもらい帰途に着いた。(矢澤孝二)
山行記録に戻る